よくあるご質問
事前相談について
事前の相談って、葬儀社の人にいやな顔されませんか?
ご不明な部分やご不安が多いのがご葬儀ですからご遠慮なくご相談ください。
ムラカミでは経済産業省認定の葬儀相談員がおりますのでご安心ください。
ムラカミでは経済産業省認定の葬儀相談員がおりますのでご安心ください。
事前相談や葬儀社をあらかじめ決めておくことは、不謹慎ではありませんか?
当社施工のご葬儀において多数の方が何らかの事前相談をされています。
ご不安点やご不明な点を解消することにより葬儀の際は慌てることなく故人様に対して想いの時間を長くお取りになれますので事前の相談等は決して不謹慎なことではないかと存じます。
ご不安点やご不明な点を解消することにより葬儀の際は慌てることなく故人様に対して想いの時間を長くお取りになれますので事前の相談等は決して不謹慎なことではないかと存じます。
何を決めておけば、慌てなくてすむのでしょうか?
まずは、万が一の際は一番初めに菩提寺様にご連絡をお願いいたします。
その後に当社にご連絡をお願いいたします。
私どもムラカミは365日24時間受付対応いたしますのでご安心ください。
病院よりご搬送の際はご自宅にお戻りになるのか、もしくは別の安置施設にてご安置になるのかをお伺いいたします。
ご自宅でない場合は当社は霊安室(やすらぎの間)を完備しております何なりとお申し付けください。
その後に当社にご連絡をお願いいたします。
私どもムラカミは365日24時間受付対応いたしますのでご安心ください。
病院よりご搬送の際はご自宅にお戻りになるのか、もしくは別の安置施設にてご安置になるのかをお伺いいたします。
ご自宅でない場合は当社は霊安室(やすらぎの間)を完備しております何なりとお申し付けください。
葬儀の知識がなく不安です。お葬式の事前準備はどうすればよいですか?
各葬儀社により価格やご葬儀の内容が異なりますので、まずは各葬儀社についてお調べいただき、説明や見積りをもらうことをおすすめいたします。
その上でまず考えなくてはいけないことは、ご葬儀の規模(訃報を知らせるところ、ご葬儀に来てもらう人数)をざっくりと決めることと、どこでご葬儀を行うか考えておくことをおすすめいたします。
また、その際喪主様や中心となる方をお決めいただくとスムーズに進みます。
いざという時慌てないためにも、下記のものをご用意しておくことをおすすめいたします。
1. 訃報連絡をする方の住所・氏名・連絡先リストを用意
2. ご安置場所の決定(自宅もしくは自宅以外)
3. 宗教の有無(宗派・宗教名、お坊さんの連絡先の用意)
4. 遺影写真(ネガではないもの)データでも可
5. 着替え用のお着物(お気に入りの服など)
6. 愛用品(お棺の中に入れてあげたいもの等、沢山ご用意することをおすすめします)
その上でまず考えなくてはいけないことは、ご葬儀の規模(訃報を知らせるところ、ご葬儀に来てもらう人数)をざっくりと決めることと、どこでご葬儀を行うか考えておくことをおすすめいたします。
また、その際喪主様や中心となる方をお決めいただくとスムーズに進みます。
いざという時慌てないためにも、下記のものをご用意しておくことをおすすめいたします。
1. 訃報連絡をする方の住所・氏名・連絡先リストを用意
2. ご安置場所の決定(自宅もしくは自宅以外)
3. 宗教の有無(宗派・宗教名、お坊さんの連絡先の用意)
4. 遺影写真(ネガではないもの)データでも可
5. 着替え用のお着物(お気に入りの服など)
6. 愛用品(お棺の中に入れてあげたいもの等、沢山ご用意することをおすすめします)
葬儀資料について
葬儀の打ち合わせの際に用意する資料とかありますか?
ご葬儀に関する資料はすべて弊社がご用意しております。
ご葬儀の流れの説明や当日のタイムスケジュール、ご納棺式に各種挨拶の例文などをまとめたムラカミオリジナルの冊子をご用意しております。
ご葬儀の流れの説明や当日のタイムスケジュール、ご納棺式に各種挨拶の例文などをまとめたムラカミオリジナルの冊子をご用意しております。
葬儀プランについて
葬儀プランとはなんですか?
ご葬儀の内容、規模等のご要望をお伺いし、ご通知の範囲からご弔問ご会葬の方々の人数をお話しさせていただきご提案させて戴く当社オリジナルのお見積もりになります。葬儀プランや祭壇・お棺をあわせると2800タイプ以上になります。さらに、大切な方のお好みに応じて祭壇の色合いや様々なメモリアルコーナーの設置もしております。ご本人らしさを演出するご葬儀が可能です。
葬儀のプランは何種類ぐらいあるのですか?
スタンダート・ミニマム・プレミアムと分かれており、合計21タイプのプランを取り揃えております。
祭壇は何種類ぐらいありますか?
生花祭壇・白木祭壇・アレンジ祭壇をご用意しており、60種類以上各種様々取り揃えております。
お棺の種類は何種類ぐらいありますか?
木製の棺・布張りの棺30種類以上各種様々取り揃えております。
やすらぎの間について
やすらぎの間とはなんですか?
諸事情によりご自宅にお戻りになれない場合、ご自宅の延長としてご利用いただける霊安室になっております。
火葬場等の霊安室はお線香や面会時間の制限がありなかなか思い通りにならないことがあります。
弊社B1Fの「やすらぎの間」にて皆様が大切な方との最後のお時間をゆっくりとお過ごしいただきたく存じます。
火葬場等の霊安室はお線香や面会時間の制限がありなかなか思い通りにならないことがあります。
弊社B1Fの「やすらぎの間」にて皆様が大切な方との最後のお時間をゆっくりとお過ごしいただきたく存じます。
やすらぎの間の面会時間はありますか?
午前10時半より午後5時半までとなっておりますが、ご遠方からのご家族の方の面会は面会時間に限らずご案内をさせていただております。
やすらぎの間にて飲食を持ち込んでもいいですか?
やすらぎの間ではお食事はご遠慮いただいております。
お飲み物のご用意もありますのでご利用ください。
お飲み物のご用意もありますのでご利用ください。
お通夜・葬儀の式場としてお借りできますか?
大変申し訳ございませんがやすらぎの間は霊安室として施設になりますので式場としてはお貸ししておりません。
お寺様をお呼びしてお経を読んで戴いてもいいですか?
お坊さんをお呼びしての読経や賛美歌はご遠慮いただいております。
やすらぎの間で故人と付き添いたいのでお泊まりは可能ですか?
宿泊はご遠慮いただいております。面会時間は午前10時半より午後5時半までとなっております。
やすらぎの間での面会は誰でも出来ますか?
契約者の範囲内でどなたでもご案内可能です。ただし、防犯の関係上ご案内の前に当社の受付にて面会者様の身分の確認をさせていただいております。ご協力お願いいたします。
葬儀について
家族葬とはどんな葬儀のことを言うのですか?
家族と言うイメージから人数を限定した葬儀と考えていただけると良いと思います。必ずしも家族だけと言う感じではなく親戚や親しい友人などが含まれる場合が多いようです。家族葬にたいして明確な会葬者の規定はありません。
家族葬のメリットは何でしょうか?
人数が限定定期になると、予め予算が予定しやすくなります。さらに不特定の会葬者がないわけですから、いわゆる追加料金に対する不安がなくなります。又、人数に左右されないと言うことで自分の考えている葬儀の実現が非常にしやすくなります。
「身内だけで、落ち着いて別れの時を過ごしたい」「心のこもった内輪だけの小さな葬儀にしたい」という思いで進めることが出来ます。
「身内だけで、落ち着いて別れの時を過ごしたい」「心のこもった内輪だけの小さな葬儀にしたい」という思いで進めることが出来ます。
密葬とはなんですか?密葬と家族葬の違いは?
密葬=「ひそかに葬ること。内々で行う葬式」──広辞苑より
本来の密葬の定義は、後日に行われる社葬を「本葬(本式の葬式)」とし、それに先行する死亡直後の(通常は個人葬として営まれる)葬儀を「密葬」と言うものであります。
大きな違いは密葬は本葬があっての儀礼式ではありますが、家族葬にはそれがありません。一般的に密葬と呼ばれているものは家族葬と密葬が混同して同義語になっており、近親者のみで執り行うご葬儀のことを家族葬もしくは密葬としての言葉で使われてます。
本来の密葬の定義は、後日に行われる社葬を「本葬(本式の葬式)」とし、それに先行する死亡直後の(通常は個人葬として営まれる)葬儀を「密葬」と言うものであります。
大きな違いは密葬は本葬があっての儀礼式ではありますが、家族葬にはそれがありません。一般的に密葬と呼ばれているものは家族葬と密葬が混同して同義語になっており、近親者のみで執り行うご葬儀のことを家族葬もしくは密葬としての言葉で使われてます。
家族葬を行う際に注意することはありますか?
家族葬には向き不向きがありますので、当社担当スタッフにご相談ください。
例えば、故人の意思を受けて家族だけで葬儀を済ませたところ、葬儀の後に参加できなかった人たちがお参りをしたいと頻繁に自宅へ訪れるようになった。訪問を断る訳にもいかず、お礼状や香典返しの準備もないなどで礼を逸してしまった上、毎週のようにその状態が続き外出もままならないなど、かえって気苦労が多くなる事態を招くことが想定されます。
歩まれた人生や環境、社会的地位などにより、家族葬が適さない場合もあることをご説明しています。本人・親族・会社・近隣・友人・趣味の活動までを確認し、しっかりと適切なアドバイスをさせていただいた上で最適な家族葬をご提案いたします。
例えば、故人の意思を受けて家族だけで葬儀を済ませたところ、葬儀の後に参加できなかった人たちがお参りをしたいと頻繁に自宅へ訪れるようになった。訪問を断る訳にもいかず、お礼状や香典返しの準備もないなどで礼を逸してしまった上、毎週のようにその状態が続き外出もままならないなど、かえって気苦労が多くなる事態を招くことが想定されます。
歩まれた人生や環境、社会的地位などにより、家族葬が適さない場合もあることをご説明しています。本人・親族・会社・近隣・友人・趣味の活動までを確認し、しっかりと適切なアドバイスをさせていただいた上で最適な家族葬をご提案いたします。
家族葬でお葬儀は、出来ますか?
はい、執り行えます。
家族だけで、故人を偲び、家族が故人と過ごす最後の時間をゆっくりと持つ事が出来ます。または近親者を含めての家族葬としても執り行えます。
義理や一切のしがらみの無いお葬式です。本当に故人の事だけを想い、みんなが納得の行く形で送ってあげるのが家族葬だと思います。
家族葬を執り行うに際して会社勤め、趣味の会等、交友関係の広い方、また、社会的地位、立場のある方の場合も、外部を完全にシャットアウトするのは難しいかもしれません。
ムラカミではご家族の方々とご相談させていただいた上でより良い家族葬を提案いたします。
家族だけで、故人を偲び、家族が故人と過ごす最後の時間をゆっくりと持つ事が出来ます。または近親者を含めての家族葬としても執り行えます。
義理や一切のしがらみの無いお葬式です。本当に故人の事だけを想い、みんなが納得の行く形で送ってあげるのが家族葬だと思います。
家族葬を執り行うに際して会社勤め、趣味の会等、交友関係の広い方、また、社会的地位、立場のある方の場合も、外部を完全にシャットアウトするのは難しいかもしれません。
ムラカミではご家族の方々とご相談させていただいた上でより良い家族葬を提案いたします。
家族葬で葬儀を執り行う場合、お布施も安くなるのですか?
家族葬は規模も人数も少ないのだから、寺院へのお布施も安くてもいいのですかとの質問がありますが、お勤めを頂くお経、戒名はご葬儀の規模に関わらず同じになります。
しかしながら、喪家様のお家の事情によりお布施の用意が困難なら一度ご住職様にご相談がよろしいかと思います。
しかしながら、喪家様のお家の事情によりお布施の用意が困難なら一度ご住職様にご相談がよろしいかと思います。
参列者が多いお葬式は、気苦労が絶えないと聞いたので、家族だけでお葬式を済ませた後、亡くなったことを知らせようと思いますが、お世話になった方々に失礼になりますか?
そういったご葬儀のやり方もありますが、亡くなったことを知らせた後に、ご自宅へ多くの方が弔問に訪れて対応に苦慮することもあるので、十分検討していただくことをおすすめします。
専門知識を持った経験豊富な当社担当スタッフにご相談ください。
専門知識を持った経験豊富な当社担当スタッフにご相談ください。
家族葬で執り行う予定ですが、もし一般参列者が来た場合はどうすればいいのでしょうか?
最初のお打ち合わせの段階で、家族のみで執り行うのか近しい方を数名招くのかをご家族様と当社担当スタッフがご相談させていただき、小さめな式場をお借りして、予定に無い一般会葬者が多数お見えになれば、入って頂く事さえも困難になり大変失礼に当たりますので、呼ぶか呼ばないか、来る可能性が有るのか無いのかを事前にしっかりと相談させていただきます。万が一、会社関係の代表者やご近所の方が数名お見えになった場合にもしっかりとした失礼のない対応をさせていただきます。どうぞご安心くださいませ。
家族葬で、お葬式を頼んだ時、費用が高い安いがあるのは、何故ですか?
喪家の事情により、火葬場の都合により、日延べによるドライアイスの追加や、霊安室の保管料、火葬場までの自家用車の使用や、ハイヤーやマイクロバスの手配であったり、ご親族同士でのお香典のやりとりの為、返礼品・料理などにより金額が、異なるものだと思われます。
施行費用が高いと感じるのであれば、もう少し出費は掛かりますが、普通のお葬式をして、一般会葬者を呼ぶと、お香典がありますので葬儀代の足しにする事は多少出来るでしょう。
ですが一番大切なのは、心を込めて送り出してあげるお気持ちになります。
ご葬儀のご予算等をご相談の上、当社担当スタッフとお打ち合わせをさせていただきます。
施行費用が高いと感じるのであれば、もう少し出費は掛かりますが、普通のお葬式をして、一般会葬者を呼ぶと、お香典がありますので葬儀代の足しにする事は多少出来るでしょう。
ですが一番大切なのは、心を込めて送り出してあげるお気持ちになります。
ご葬儀のご予算等をご相談の上、当社担当スタッフとお打ち合わせをさせていただきます。
家族葬は、どの会社も安価な値段が多い様に感じますが、私は母をお花で飾ってあげたいと思うのですが、そういった事は出来るのですか?
最近、生花祭壇の需要も高まり、多種多様な生花祭壇を当社では取り揃えております。
祭壇のお花やお花の色をご希望にお応えいたします。
生花祭壇は白木の祭壇よりも、イメージ的に華やかにお式を執り行う事が出来ます。
祭壇のお花やお花の色をご希望にお応えいたします。
生花祭壇は白木の祭壇よりも、イメージ的に華やかにお式を執り行う事が出来ます。
家族葬と一般葬の違いは?
家族葬は、ご家族・ご親族・親しい知人のみで故人様を送る、心温かい葬儀の形です。身内だけなので慌ただしさがなく、その分故人様とのお別れの時間を大切にできるのが特徴です。
一般葬は、身内だけで葬儀を行うのでなく、親しい知人やご近所、会社関係の方など多くのご会葬の方で送る、一般的な葬儀です。お世話になった方々に、しっかりとお別れをして頂く事が出来ます。
一般葬は、身内だけで葬儀を行うのでなく、親しい知人やご近所、会社関係の方など多くのご会葬の方で送る、一般的な葬儀です。お世話になった方々に、しっかりとお別れをして頂く事が出来ます。
少人数の家族葬でも、事前の相談や葬儀の依頼を受けていただけますか?
もちろん承ります。少人数だからこそ、適切な広さの葬儀場を提案させていただくなど、ご家族の不安を解消し、しっかりとお見送りが出来るお手伝いをさせていただきます。
家族だけのお葬式は、ご近所や友人の方などに対して、失礼にあたりますか?
家族葬は、最近増えてきているご葬儀で、弊社でお手伝いさせていただくご葬儀でも家族葬の割合が増えてきております。誰にも知らせずに、家族でご葬儀を済ませる方法もありますが、身内だけで葬儀をするので参列をご辞退いただくことを伝えて、家族だけでご葬儀をする方法もあります。ご家族のご要望にあった対応をご提示いたしますので、ご安心ください。
家族葬で香典や供花を、いただいてもよろしいのでしょうか?
特に問題はありません。ご辞退ご希望の際は、事前にお伝えするようにお願いしております。
家族葬とは、親戚のどこまで声をかければよろしいでしょうか?また人数の制限はありますか?
人数などに、決まりはありません。家族葬とは、形式的なことに時間や手間をかけるのでなく、ご家族の方が気兼ねなく、温かく送ることが出来るご葬儀のことなので、家族葬に特に親しい方をお招きすることも多くなっております。
家族葬をしたいので、亡くなったことを近所に知られないようにすることは可能ですか?
可能です。亡くなったら一般的には、一度ご自宅に戻りますが、ご自宅に戻らずに安置施設へご安置すれば、ご近所の方に知られることはありません。またご自宅安置を希望の場合は、早朝や夜間など、人目のない時間帯でご安置、移動をすることも可能です。ご自宅でのご葬儀の打ち合わせも当社スタッフは細心の注意を払います。
ご希望の方は当社スタッフまでお申し付けください。
ご希望の方は当社スタッフまでお申し付けください。
自宅で、誰にも知られないで家族葬を執り行なう事は出来ますか?
難しいと思います。たしかに、会場費などの事を考えると低料金では執り行なえますが、自宅・地元の集会所・自治会館を利用した場合、ご近所様との付き合いを皆無にする事は出来ないでしょう。
一般葬のデメリットはありますか?
特にありませんが、参列者人数の予想が難しいことは事実です。
弊社では、参列者人数を出来るだけ正確に予想をするようにお手伝いさせていただきます。また、急に予想を上回る参列者がいらっしゃった時に、万全の対応が出来るように準備をさせていただきますので、ご安心ください。
弊社では、参列者人数を出来るだけ正確に予想をするようにお手伝いさせていただきます。また、急に予想を上回る参列者がいらっしゃった時に、万全の対応が出来るように準備をさせていただきますので、ご安心ください。
予想人数を下回った場合、どんなデメリットがありますか?
参列者にご迷惑を掛けることはありませんが、余った料理は返品不可能なので、ご了承ください。ただ、返礼品については、返品可能なのでご安心ください。
大型葬をスムーズに行うポイントを教えてください。
しっかりとした準備です。そのために、亡くなってから最低2日以上あけて葬儀を行うことを、おすすめしています。
多くの方を招く大型葬は、まず葬儀の日時・場所の連絡を漏れなく行うことから始まります。人数が多いと訃報が知れ渡ることに時間を要するので、日程をあけることは参列者の方々への配慮です。受付・会計などのお手伝い係の手配も必要となるので、余裕を持った葬儀日程をおすすめしております。
葬儀までの数日間、故人様のお体のケアは、弊社にて万全に行うのでご安心ください。
多くの方を招く大型葬は、まず葬儀の日時・場所の連絡を漏れなく行うことから始まります。人数が多いと訃報が知れ渡ることに時間を要するので、日程をあけることは参列者の方々への配慮です。受付・会計などのお手伝い係の手配も必要となるので、余裕を持った葬儀日程をおすすめしております。
葬儀までの数日間、故人様のお体のケアは、弊社にて万全に行うのでご安心ください。
会社の代表や役員が亡くなったら社葬をやるのですか?
社葬とは、企業が葬儀費用を負担して、葬儀を取り仕切る葬儀のことです。
会社の代表者の方であっても、ご家族が窓口になり、ご家族が葬儀費用を負担するのであれば、個人葬となります。
社員のご葬儀であっても、会社が葬儀費用を負担する場合は、社葬となります。
会社の代表者の方であっても、ご家族が窓口になり、ご家族が葬儀費用を負担するのであれば、個人葬となります。
社員のご葬儀であっても、会社が葬儀費用を負担する場合は、社葬となります。
社葬をスムーズに行うポイントを教えてください。
しっかりとした準備です。そのために、亡くなってから最低2日以上あけて葬儀を行うことを、おすすめしています。
多くの方を招く社葬は、まず葬儀の日時・場所の連絡を漏れなく行うことから始まります。人数が多いと訃報が知れ渡ることに時間を要するので、日程をあけることは、お取引先や参列者の方々への配慮です。受付・会計などのお手伝い係の手配も必要となるので、余裕を持った葬儀日程をおすすめしております。
特に来賓(VIP)への対策は欠かせないので、人員配置、オペレーションの確認をしっかり行います。葬儀までの数日間、故人様のお体のケアは、弊社にて万全に行うのでご安心ください。
多くの方を招く社葬は、まず葬儀の日時・場所の連絡を漏れなく行うことから始まります。人数が多いと訃報が知れ渡ることに時間を要するので、日程をあけることは、お取引先や参列者の方々への配慮です。受付・会計などのお手伝い係の手配も必要となるので、余裕を持った葬儀日程をおすすめしております。
特に来賓(VIP)への対策は欠かせないので、人員配置、オペレーションの確認をしっかり行います。葬儀までの数日間、故人様のお体のケアは、弊社にて万全に行うのでご安心ください。
火葬式とは、どんなお葬式ですか?
通夜・葬儀を執り行わないご葬儀のことです。荼毘のみになります。
火葬式はどこで式を行うのですか?
火葬場、もしくはご自宅になります。
火葬場では直接にご火葬炉の前になりますので故人様とのお別れのお時間をお取りすることが難しくなります。
ご自宅の場合ですと出棺までのお時間がお別れのお時間となります。
火葬場では直接にご火葬炉の前になりますので故人様とのお別れのお時間をお取りすることが難しくなります。
ご自宅の場合ですと出棺までのお時間がお別れのお時間となります。
参列者人数に制限はありますか?
制限はありませんが、少人数で執り行うことが多いです。
戒名をいただきたいのですが、火葬式でも戒名をいただくことができますか?
火葬式はご住職に読経いただくこともできますし読経はしないで戒名だけいただくこともできます。しかし、火葬式をお決めする前にご住職とご相談の上で進めさせていただきます。
無宗教葬では、どんな儀式をするのでしょうか?
代表的な儀式は献花と呼ばれる、お花を供える儀式です。仏教では、お経やお焼香がありますが、無宗教では決まりがありませんので、亡くなった方の好きな音楽を流すなど、ご家族と打合せをしながら儀式の内容を決定します。
無宗教葬の経験豊富な当社担当スタッフがアドバイスするので、ご安心ください。
無宗教葬の経験豊富な当社担当スタッフがアドバイスするので、ご安心ください。
無宗教葬の費用は、仏教のお葬式より安くなりますか?
寺院様へのお布施の費用の負担が無くなります。
ご会葬者への接待等のご負担は仏式のご葬儀と変わりません。
ご希望に合わせましてお見積もりを作成いたします。何なりとお申し付けくださいませ。
ご会葬者への接待等のご負担は仏式のご葬儀と変わりません。
ご希望に合わせましてお見積もりを作成いたします。何なりとお申し付けくださいませ。
無宗教で送りたいのですが可能でしょうか?
無宗教の葬儀は自由な反面、ある程度のシナリオを設定する必要があります。ご希望や想いを元に式自体をつくり上げて行く流れが一般的です。例えば、故人の趣味や写真コーナーを作り、思い出の曲を流しながら故人を偲び参列者が思い出話しを語るなど色々なことが可能です。
しかし、無宗教で葬儀を行える方は限られています。親戚の理解やお墓との関係など、諸条件をクリアしなければトラブルの原因となりますので注意が必要です。無宗教葬儀の注意点をおさえ、お客様が後々も困らないように配慮しながら、ご要望にそった無宗教の葬儀をご提案いたします。
しかし、無宗教で葬儀を行える方は限られています。親戚の理解やお墓との関係など、諸条件をクリアしなければトラブルの原因となりますので注意が必要です。無宗教葬儀の注意点をおさえ、お客様が後々も困らないように配慮しながら、ご要望にそった無宗教の葬儀をご提案いたします。
葬儀に期限ってあるの?
書類の死亡届などは提出期限等はあります。死亡の事実を知った日から7日以内になります。エンバーミングという技術があってもずっと故人のお体を維持できるものではありませんので早めにこの後どうするかというのはお決めになったほうが良いでしょう。
いつ葬儀をするなどについては概念にとらわれなくても最終的に葬儀を終えたときに悔いが残らないようにするのが一番いいお葬儀ではないでしょうか。
いつ葬儀をするなどについては概念にとらわれなくても最終的に葬儀を終えたときに悔いが残らないようにするのが一番いいお葬儀ではないでしょうか。
葬儀の日程はどのように決まるのですか?
以下の4つを確認し、すべての条件を満たした日付が、葬儀の日程となります。
- ご家族のご都合
- お坊さん(ご住職など)のご都合
- 式場の空き状況
- 火葬場の空き状況
葬儀ができない日を教えてください。
暦の六曜の友引の日になります。「葬儀ができない日」とは「火葬ができない日」を表しますので、お通夜は可能です。なぜなら友引は、火葬場が休みのところが多いので、告別式(火葬)ができません。
お通夜は亡くなった日にするものなのでしょうか?
通常は、お亡くなりになられた日の翌日以降になります。もちろん、ご家族様のご希望等があれば、少々慌ただしくはなってしまいますが、お手伝いさせていただきます。
ただし、菩提寺様のご都合と火葬場のご火葬炉の申し込み等の条件が揃った際になります。
ただし、菩提寺様のご都合と火葬場のご火葬炉の申し込み等の条件が揃った際になります。
葬儀の日取りに決まって「友引」という言葉を耳にしますが、どういういわれがあるのですか?
友引は六輝(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)のひとつで、本来は「勝負なし、共に退く」という意味であります。
これが、俗信として、その文字の表す通り、この日の葬儀をすると「友を死に引く、または死に誘う」というようにこじつけ、死忌と結びつけてこの日を忌み嫌うようになったのです。
これが、俗信として、その文字の表す通り、この日の葬儀をすると「友を死に引く、または死に誘う」というようにこじつけ、死忌と結びつけてこの日を忌み嫌うようになったのです。
友引に葬儀をしてはいけないのでしょうか?
友引に葬儀をしてはいけないことはありませんが、火葬場が休場していることが多く、友引の日に葬儀(火葬)できない地域があります。また、ご年配の方を含め「友を引く」というニュアンスを気にされる方もいらっしゃいますので、親戚・関係者などに配慮しながら決めるのが良いでしょう。
ご家族のみなど小規模な場合には、友引でも行われていますが、ある程度の方々が参列するお葬式では、お越しの方の心情を考えて角を立てないようにと、避ける場合が多いようです。
ご家族のみなど小規模な場合には、友引でも行われていますが、ある程度の方々が参列するお葬式では、お越しの方の心情を考えて角を立てないようにと、避ける場合が多いようです。
友引に火葬できないのはなぜ?
陰陽道で凶禍が友人に及ぶとする方角又は六曜の一つで何をしても勝負がつかないとする日。一般的には、友を呼ぶもしくは共に引き合うと言い伝えられ地域によっては通夜も避ける習慣があるようです。
近年、火葬場が休みとなっていて火葬することができなくなっていましたが、友引でも運営をしている火葬場もあるようです。お近くですと臨海斎場になります。
近年、火葬場が休みとなっていて火葬することができなくなっていましたが、友引でも運営をしている火葬場もあるようです。お近くですと臨海斎場になります。
「友引」の日に、お通夜をしてもよいのでしょうか?
はい、可能です。友引とは「お通夜ができない日」ではなく「火葬ができない日」を意味しますので、お通夜を執り行うことは問題ありません。
平日、仕事を切り上げてお葬式に来てもらうのは申し訳ない気がするのですが?
土日など、職場が休日の日に日程を調整する方法がございます。
菩提寺様のお勤めのご都合をお伺いし当社担当スタッフが日程の調整をいたします。
弊社では、日程を先に延ばされても、ご遺体が傷まぬよう対応いたしておりますので、ご安心ください。
菩提寺様のお勤めのご都合をお伺いし当社担当スタッフが日程の調整をいたします。
弊社では、日程を先に延ばされても、ご遺体が傷まぬよう対応いたしておりますので、ご安心ください。
帰国する息子を待ってお葬式をしたいのですが、どのくらい待っていただけるのでしょうか?
特に期限はございません。1週間程度待つことはそれほどめずらしくありません。
ご遺体の状況にもよりますが当社スタッフより処置を施し状態を安定させるためのご提案をし、ご葬儀の当日を迎えられるようにいたします。
ご遺体の状況にもよりますが当社スタッフより処置を施し状態を安定させるためのご提案をし、ご葬儀の当日を迎えられるようにいたします。
もしもの時、すぐに必要なものは何ですか?
慌てる必要はありませんが取り急ぎ必要になるものをご案内します。遺影として使用するお写真、印鑑をご用意ください。お写真はピントが合い表情がよいものを選びましょう。印鑑は認印でかまいませんがシャチハタは不可になります。印鑑は、市区役所へ死亡届を提出する際に使用します。印鑑はなるべく金融機関でお使いでない物をお預かりいたします。その他は、場面ごとの必要事項になりますので当社担当スタッフにご相談ください。状況に応じて丁寧にお手伝いいたします。
参列者人数の予想ができません。予想の手順を教えてください。
まず、家系図を書いて親族の人数を予想します。親族の人数は、比較的容易に把握できます。続いて、亡くなった方の関係者を予想します。年賀状や携帯電話のメモリーを参考にしながら、ご友人、ご近所の方、会社関係、サークル関係など、いくつかの区分に分けて5人、10人など概算で予想をします。その後、ご家族の関係者を、亡くなった方と同じように、いくつかの区分に分けて予想をしていきます。
(※区分:友人、仕事、ご近所、喪主様仕事、習い事、お子様関係など)
(※区分:友人、仕事、ご近所、喪主様仕事、習い事、お子様関係など)
遺影写真はどのようなものを用意すればよいですか?
1. 笑顔が素敵なお写真
2. 旅行での楽しい時のお写真
3. ご家族やお孫様とのお集まりの時のお写真
4. お気に入りの服や好きな帽子などを被っているお写真
一枚だけでなく出来れば数枚お選びください。当社担当スタッフと検討させていただき、よりよいご遺影をお作りするお手伝いをいたします。
当社ではご遺影は大切な方とのお時間を切り抜いて映し出すものと考えております。皆様方でお時間の許す限り様々なお写真をご検討ください。
2. 旅行での楽しい時のお写真
3. ご家族やお孫様とのお集まりの時のお写真
4. お気に入りの服や好きな帽子などを被っているお写真
一枚だけでなく出来れば数枚お選びください。当社担当スタッフと検討させていただき、よりよいご遺影をお作りするお手伝いをいたします。
当社ではご遺影は大切な方とのお時間を切り抜いて映し出すものと考えております。皆様方でお時間の許す限り様々なお写真をご検討ください。
喪主は誰が務めるのがいいのでしょうか?
喪主はご遺族で協議して決定します。一般的には故人の配偶者、長男、長女という順番で近い方が務めます。配偶者や子供がないときは親兄弟が務め、高齢などの場合には実務を代役の方がサポートして行われます。迷う時には、ご相談ください。ご関係に応じて良い方法をご提案いたします。
ご関係が複雑な場合などは迷われることもあるでしょう。更に喪主と施主は違いがあります。喪主はお葬式の実務的な部分の代表となり、大きな役割としては参列者へのご挨拶・お礼状に名前が印刷される・出棺の時の挨拶などがあげられます。喪主の役割は分担しても行われますし、金銭的な面の代表となる施主を兼ねる場合も多くあります。
ご関係が複雑な場合などは迷われることもあるでしょう。更に喪主と施主は違いがあります。喪主はお葬式の実務的な部分の代表となり、大きな役割としては参列者へのご挨拶・お礼状に名前が印刷される・出棺の時の挨拶などがあげられます。喪主の役割は分担しても行われますし、金銭的な面の代表となる施主を兼ねる場合も多くあります。
喪主になると何をしなければいけないのですか?
「喪にふくす主(あるじ)」という意味で、会葬者様への挨拶などをするご家族代表者となります。喪主の類似語で"施主"という役割があり、「布施する主」という意味で、費用負担・運営の責任者となります。
ただ、喪主の役割は明確なものがなく、施主やその他のご家族が挨拶をするケースもございます。
<例>故人:父、喪主:母、施主:長男の場合
葬儀打合せや挨拶は「施主:長男」、葬儀費用負担は「喪主:母」となる場合もございます。
ただ、喪主の役割は明確なものがなく、施主やその他のご家族が挨拶をするケースもございます。
<例>故人:父、喪主:母、施主:長男の場合
葬儀打合せや挨拶は「施主:長男」、葬儀費用負担は「喪主:母」となる場合もございます。
「子供一同」など身内でも生花を出すものですか?
出すことが多いですが、宗教的な決まりごとはございません。また、関東地域では「喪主花(喪主様が出す生花)」は一般的ですが、その習慣がない地域もあります。
席順やお花の順番ってどう決めてるの?
席順などの配列はやはり問題になってきます。仏事にも上座、下座が存在します。
祭壇に向かって右側が上になり向かって左が下になります。
このことから席順も血縁関係の濃い方より右側の前列の内側から座って頂くほうが多いです しかし遺族の方の考えしきたりによっても異なりますのでこれが決まりではありません。同様に生花もそうです。
血縁の濃い方の生花から 祭壇を挟み最上段右列の内側、最上段左列の内側上段が生花で埋まると次は中段から下段へ・・・というのが多いです。
祭壇に向かって右側が上になり向かって左が下になります。
このことから席順も血縁関係の濃い方より右側の前列の内側から座って頂くほうが多いです しかし遺族の方の考えしきたりによっても異なりますのでこれが決まりではありません。同様に生花もそうです。
血縁の濃い方の生花から 祭壇を挟み最上段右列の内側、最上段左列の内側上段が生花で埋まると次は中段から下段へ・・・というのが多いです。
弔辞は誰に頼めばいいのですか?
葬儀の中で弔辞を呼んでもらう時間を用意している場合は、遅くとも葬儀の前日までには依頼して了承を得ておく必要があります。故人が生前、特に親しくしていた友人や仕事上でのつきあいの深かった人にお願いをされていることが多いようです。
忌中紙(きちゅうし、玄関先へ貼る訃報の知らせ)はいつ貼り出すものですか?
ご葬儀日程や場所が決まり次第貼り出すものですが、その知らせにより通夜・告別式で自宅を留守にすることが分かるので防犯の観点から、貼り出さないケースが多くなっています。
喪服は、レンタルできますか?
喪服を手配いたします。葬儀の打合せの際に、当社担当スタッフにお問合せください。
女性の和服は、着付けなどもあわせてご相談ください。急な場合や直前の手配ですと間に合わないことも想定されますので、なるべく早めのご連絡をお願いします。
女性の和服は、着付けなどもあわせてご相談ください。急な場合や直前の手配ですと間に合わないことも想定されますので、なるべく早めのご連絡をお願いします。
アクセサリーなどはすべて外さないといけないのですか?
時計など必要なものがありますので、あまり派手にならない程度で対応するのが望ましいと思われます。
喪服の他に必要なものはありますか?
数珠をご用意ください。数珠はどんなものでも構いません。故人様の使っていたものは、棺に入れる方もいますが、形見としてそのまま利用する方もいらっしゃいます。
棺に故人の好きだったものを納めたいのですが。
基本的に燃える物を副葬品としてお願いしております。
故人様が愛用された物の中には、CO2やダイオキシン等の公害を発生させる物や設備の故障原因となるため、棺に納めることが出来ない物があります。判断が付きづらい副葬品は一度ご用意ください。当社担当スタッフが判断させていただきます。
故人様が愛用された物の中には、CO2やダイオキシン等の公害を発生させる物や設備の故障原因となるため、棺に納めることが出来ない物があります。判断が付きづらい副葬品は一度ご用意ください。当社担当スタッフが判断させていただきます。
棺にいれていいものって?
基本的には火葬できないものは入れることはできないと考えてください。
火葬場からのお願いによると
(1)公害の発生源となるもの
・ビニール製品 ハンドバック、靴など
・化学合成繊維製品 衣類、寝具、敷物など
・発泡スチロール製品 枕など
・その他 CD、ゴルフボールなど
(2)可燃物であるが燃焼の妨げになるもの
・果物 スイカ、メロンなどの大きい果物
・書物 辞書、アルバムなどの厚みのある書物類
・大型繊維製品 衣類の納め過ぎ、大きなぬいぐるみなど
(3)火葬路設備の故障原因となるもの
・カーボン製品 杖、釣り竿、ゴルフクラブ、ラケットなど
(4)遺骨の損傷の原因になるもの
・金属製品 携帯ラジオ、カセット、各種電化製品、仏像など
・ガラス製品 鏡、食器類など
・爆発物 缶飲料、化粧品スプレー、ライターなど
*ペースメーカーを使用の場合には前もってご連絡ください。
火葬できるものでもお骨の損傷につながるものも入れることはできないのです。
もし火葬できないものを持たせてあげたいと言う場合は骨壷の中に入れてあげると言うことも可能です。
火葬場からのお願いによると
(1)公害の発生源となるもの
・ビニール製品 ハンドバック、靴など
・化学合成繊維製品 衣類、寝具、敷物など
・発泡スチロール製品 枕など
・その他 CD、ゴルフボールなど
(2)可燃物であるが燃焼の妨げになるもの
・果物 スイカ、メロンなどの大きい果物
・書物 辞書、アルバムなどの厚みのある書物類
・大型繊維製品 衣類の納め過ぎ、大きなぬいぐるみなど
(3)火葬路設備の故障原因となるもの
・カーボン製品 杖、釣り竿、ゴルフクラブ、ラケットなど
(4)遺骨の損傷の原因になるもの
・金属製品 携帯ラジオ、カセット、各種電化製品、仏像など
・ガラス製品 鏡、食器類など
・爆発物 缶飲料、化粧品スプレー、ライターなど
*ペースメーカーを使用の場合には前もってご連絡ください。
火葬できるものでもお骨の損傷につながるものも入れることはできないのです。
もし火葬できないものを持たせてあげたいと言う場合は骨壷の中に入れてあげると言うことも可能です。
忌日、逮夜とは?
亡くなった命日から四十九日までの、七日ごとの法要の日や、命日を忌日(きび)といいます。
また忌日やお通夜の前日をお逮夜(たいや)と呼び、どちらも大切な日として扱います。
また忌日やお通夜の前日をお逮夜(たいや)と呼び、どちらも大切な日として扱います。
遺族が気にしなくてはいけない葬儀のマナーってありますか?
ご親戚や親しい方も含めて、ご会葬に来ていただいた方や、お花・弔電などで心遣いしていただいた方へのお礼をしっかりされることが大切です。
時には細かいことを指摘される方もいらっしゃいますが、地域の慣習が要因である場合も多いものです。お見送りに対するお考えが違う方が周囲にいらっしゃっても、お気持ちをしっかりとご説明して礼を尽くすことで、きっと温かく受け止めていただけることでしょう。
時には細かいことを指摘される方もいらっしゃいますが、地域の慣習が要因である場合も多いものです。お見送りに対するお考えが違う方が周囲にいらっしゃっても、お気持ちをしっかりとご説明して礼を尽くすことで、きっと温かく受け止めていただけることでしょう。
お葬式の際の服装を教えてください。
男性:黒もしくは黒に近いスーツ、白シャツ、黒ネクタイ、黒靴下、黒靴です。全体が黒の印象にまとまれば細かいことは気にする必要はありません。
女性:黒の服装であれば、問題ありません。正式には、喪服(和装)を着ますが、実際の葬儀のときには、移動がたくさんあるので、動きやすい服装が多くなっております。
女性:黒の服装であれば、問題ありません。正式には、喪服(和装)を着ますが、実際の葬儀のときには、移動がたくさんあるので、動きやすい服装が多くなっております。
葬儀の前に自宅へ会葬に来る方がいます。喪服を着て迎えた方がよいのでしょうか?
平服で構いません。迎える側が平服であれば、先方様へ気を使わせることがありません。
香典を受け取る受付や会計のお手伝いは誰に頼めばよろしいでしょうか?
基本的には誰がしてはいけないという事は有りませんのでご親族の方でもマナー違反にはなりませんが、知人の方や友人の方に頼まれてもよろしいかと思います。 ご親戚の方がなされても良いのですが、通夜や告別式の際に遺族として席につかれる方には受付のお手伝いはご遠慮いただいております。但し、お香典の現金を預かりますので会計には一人ご親族が良い場合もあります。
受付や会計の方への謝礼の金額は?
お手伝いのお礼の目安は、1人あたり3,000円~5,000円の金額が多いです。
生花祭壇を選ぶ方は、どのくらいいらっしゃいますか?
約8~9割の方がお選びになっております。
なぜ生花祭壇を選ぶ方が多いのですか?
近年、ご家族だけのお葬式が増え、参列者からいただく供花(名札を立てた花)の数が減っております。その花を補うために、生花祭壇を選ぶ方が増えています。また、白木祭壇のイメージがお気に召さない方も多いようです。
生花祭壇はお花に囲まれて故人を送る事が出来るのも選ばれてる要因の一つです。
生花祭壇はお花に囲まれて故人を送る事が出来るのも選ばれてる要因の一つです。
故人の好きだった花で祭壇の飾ることは出来ますか?
はい。最近では、お葬式の祭壇に色とりどりのお花を飾る事が多くなってきました。
故人の好きだったお花、故人の人柄が偲ばれるお花など、色々なアレンジが出来ますので、当社担当スタッフまでご相談ください。
故人の好きだったお花、故人の人柄が偲ばれるお花など、色々なアレンジが出来ますので、当社担当スタッフまでご相談ください。
どのくらいの方がラストケア(メイク)サービスを依頼しますか?
弊社では約8割以上の方にご利用いただいております。ご利用いただいたお客様の満足度は非常に高く、自信をもっておすすめします。
湯かんはどこで実施するのですか?
湯かんの道具は、移動式の車で運搬することができるので、葬儀場、ご自宅など、皆様のご都合や希望に応じて対応します。
旅支度とは何ですか?
故人様の旅立ちの身支度のこと意味します。亡くなった方を白装束に着せ替え、足袋を履かせるなど、ご家族が、亡くなった方の身支度を整えます。
死化粧や湯かんを希望します。どのようにすればいいですか?
お葬式の打合せの中で、当社担当スタッフがご家族のご要望をお伺いいたします。その時にご希望の旨をお伝えください。
告別式の弔辞を依頼されましたが心得や書き方について教えてください。
弔辞を依頼されたら、何名の弔辞があるかを確認し、2~3名の時内容が重複しないように注意し、巻紙か奉書に黒か薄墨で丁寧に清書します。薄く書くのは「追悼の辞」「お別れのことば」と書きます。弔辞は、故人の生前の業績や人柄などをたたえ、その死を惜しむ気持ちを述べるものです。
お通夜に出かける場合は、どうすればよいですか?
用意があれば礼服で、開式時間に合わせて出かけます。お参りを済ませた後もしばらく遺族の方と過ごすのが普通です。
また、通夜振る舞いを勧められたら断らないのがマナーです。但し、お酒はほどほどにし、車などの時はお酒は辞退します。
最近は勤務の関係でお葬式に出かけられない場合、お通夜に出かける事が多くなって参りました。
また、通夜振る舞いを勧められたら断らないのがマナーです。但し、お酒はほどほどにし、車などの時はお酒は辞退します。
最近は勤務の関係でお葬式に出かけられない場合、お通夜に出かける事が多くなって参りました。
お通夜にはどのような心構えが必要ですか?
通夜の会場では遺族の悲しみを察して、大声で話したり、高笑いをしたりしてはいけません。歯を見せて笑わない慎み深い態度を保つことです。通夜のあと通夜ぶるまいに残るのは、故人と特に親しかった人だけ、というのが原則です。親交のなかった人は、読経、焼香が終わりましたら帰えるのが常識で、勧められもしないのに、いつまでも残っているようなことがないようにします。
通夜ぶるまいでは、故人の思い出話をしんみりとなつかしく交わすし、話題は故人と関連のあるものにして、無関係な話は極力避けます。
通夜ぶるまいでは、故人の思い出話をしんみりとなつかしく交わすし、話題は故人と関連のあるものにして、無関係な話は極力避けます。
香典の表書きは、どのように書けばよいですか?
香典の表書きは水引を境にして上に仏式なら「御香典」「御仏前」「御香料」。神式なら「御玉串料」「御神饌料」「御榊料」、キリスト教なら「御花料」「御弔慰料」などとします。
そして下部の中央よりやや左よりに姓と名を書きます。右肩に小さく住所を書き添えるのが遺族に対して親切です。
また、香典包みの裏に金額を書いておくのが常識です。
そして下部の中央よりやや左よりに姓と名を書きます。右肩に小さく住所を書き添えるのが遺族に対して親切です。
また、香典包みの裏に金額を書いておくのが常識です。
香典の金額の目安はどれほどでしょうか?
ある調査では香典として包む金額は、一番多いのが5千円、次に1万円、3千円の順です。
親兄弟など関係の深い場合は、金額的にはいくぶん少ない傾向もあるようですが、そのかわり喪家へのお手伝いなどの奉仕活動で提供してもらえると考えてよいでしょう。
親兄弟など関係の深い場合は、金額的にはいくぶん少ない傾向もあるようですが、そのかわり喪家へのお手伝いなどの奉仕活動で提供してもらえると考えてよいでしょう。
供花、お供え物はどの様に手配すれば良いのですか?
供花や盛り籠は会場の飾りつけの都合がありますので、早めに葬儀会社に連絡するか場合によっては喪家に申し出ます。
その時に、贈り物の名前をどのように記載してもらうかをしっかりと伝えましょう。
お菓子や線香を直接持参してお参りする場合もあります。
その時に、贈り物の名前をどのように記載してもらうかをしっかりと伝えましょう。
お菓子や線香を直接持参してお参りする場合もあります。
一般会葬者の服装を教えてください。
一般の会葬者は通夜の席には平服で出ても構いませんが、なるべく地味な色柄にして男性は黒、紺、ダークグレー等の背広を着用し、ネクタイと靴は必ず黒にしましょう。
女性も和服なら地味な普段着に黒の帯にしましょう。洋服なら地味な普段着に黒の靴にしましょう。
女性も和服なら地味な普段着に黒の帯にしましょう。洋服なら地味な普段着に黒の靴にしましょう。
葬儀に参列できない場合、どうすればよいのですか?
なにかの事情でお葬式に出られなかった場合は、代理人に名刺を持たせて参列させるか、後ほど手紙を添えて香典を郵送します。
その場合、不祝儀袋に包んだものを現金書留にしてお届けします。また、式の後にお悔やみに出かける場合もあります。
その場合、不祝儀袋に包んだものを現金書留にしてお届けします。また、式の後にお悔やみに出かける場合もあります。
香典は、共同で出してもよいのでしょうか?
遺族・親族の皆様はお香典返しの等の返礼やさまざま事後の御挨拶及びに整理に忙しい思いをします。
なるべく葬儀後の煩わしさを省いてあげるために、やむ得ない場合の他は、なるべく共同で包まないようにするのが親切だと思います。
但し、葬儀後に香典返しを発送する習慣のない所は、共同でもかまいませんが、各人の住所は記載すべきでしょう。
なるべく葬儀後の煩わしさを省いてあげるために、やむ得ない場合の他は、なるべく共同で包まないようにするのが親切だと思います。
但し、葬儀後に香典返しを発送する習慣のない所は、共同でもかまいませんが、各人の住所は記載すべきでしょう。
宗教について
自分の家の宗派が分かりません。
まずは、菩提寺様にお伺いしてみてください。
お墓がなく、ご先祖様もいない場合は、ご実家の宗派に合わせるのが一般的ですが、ご住職のお人柄やお寺の場所等が気に入れば そちらを菩提寺としてお付き合いをされるのも良いでしょう。
今後長いおつきあいになりますので焦らずにご検討ください。
お墓がなく、ご先祖様もいない場合は、ご実家の宗派に合わせるのが一般的ですが、ご住職のお人柄やお寺の場所等が気に入れば そちらを菩提寺としてお付き合いをされるのも良いでしょう。
今後長いおつきあいになりますので焦らずにご検討ください。
家族葬で執り行い、お寺さんは、呼ばない予定ですが、その場合位牌は、どうなるのですか?
戒名は、お寺さんに授けてもらい、お位牌に書いてもらうのでお寺さんを呼ばれない場合は、戒名・初七日・逮夜表(日程表)などはありません。
寺院様をお呼びしない場合は白木の位牌に俗名で式を執り行う場合もあります。
今後のご埋葬法要やお盆や一周忌などご法要の追善供養の際にお経も頼みにくくなるので、ご葬儀のお打ち合わせ時に当社担当スタッフにご相談ください。
寺院様をお呼びしない場合は白木の位牌に俗名で式を執り行う場合もあります。
今後のご埋葬法要やお盆や一周忌などご法要の追善供養の際にお経も頼みにくくなるので、ご葬儀のお打ち合わせ時に当社担当スタッフにご相談ください。
神道葬の作法を教えてください。
仏教葬では必ず霊前へのご焼香が行われますが、神道葬ではお焼香は行いません。
神道葬では玉串奉奠(たまぐしほうてん)という、玉串と呼ばれる葉のついた枝を神前にお供えします。
1. 神官または係員から玉串をいただく。葉先が左、根元が右の形で渡されるので、葉を左掌で受け、右手で上から茎をつまむようにして受け取る。
2. 胸の前で保持しながら祭壇に向かって進む。
3. 玉串案の前で止まり、葉先が向こうに、根元が手前になるように右回りに回しながら左手を根元まで下げ、右手を葉先のほうに持ちかえて、更に180度右回りに回して完全に根元が霊前に向くようにして玉串案の上に捧げるようにおく。
4. 深く二礼し、二拍手し、もう一度深く一礼する。
5. 二、三歩後ずさりして軽く一礼する。
6. あとの参列者の邪魔にならないように、玉串案から離れ、右側の喪主の前に人がいないようなら、近づいて一礼する。
7. 親族の列に軽く会釈しながら退出する。
神道葬では玉串奉奠(たまぐしほうてん)という、玉串と呼ばれる葉のついた枝を神前にお供えします。
1. 神官または係員から玉串をいただく。葉先が左、根元が右の形で渡されるので、葉を左掌で受け、右手で上から茎をつまむようにして受け取る。
2. 胸の前で保持しながら祭壇に向かって進む。
3. 玉串案の前で止まり、葉先が向こうに、根元が手前になるように右回りに回しながら左手を根元まで下げ、右手を葉先のほうに持ちかえて、更に180度右回りに回して完全に根元が霊前に向くようにして玉串案の上に捧げるようにおく。
4. 深く二礼し、二拍手し、もう一度深く一礼する。
5. 二、三歩後ずさりして軽く一礼する。
6. あとの参列者の邪魔にならないように、玉串案から離れ、右側の喪主の前に人がいないようなら、近づいて一礼する。
7. 親族の列に軽く会釈しながら退出する。
神道に戒名はありますか?
御霊となった故人様のお名前として、生前のお名前に加え、諡号(おくりな)をつけます。
成人男性は「大人命(うしのみこと)」、成人女性は「刀自命(とじのみこと)」などが一般的な諡号ですが、神主様が故人様のご年齢、生前のお考え、ご家族の希望などをもとに決めていきます。
戒名とは違い、諡号にランクはございません。
成人男性は「大人命(うしのみこと)」、成人女性は「刀自命(とじのみこと)」などが一般的な諡号ですが、神主様が故人様のご年齢、生前のお考え、ご家族の希望などをもとに決めていきます。
戒名とは違い、諡号にランクはございません。
神主さんを紹介していただけますか?
はい。ご紹介可能です。
神道のお葬式の式次第を教えてください。
神道葬も、仏教と変わりません。ただ宗教の違いがあるので、呼び方の違いがあったり、雰囲気が違ったりしますが、ご家族が困るような大きな違いはありません。お参りの仕方が、お焼香が玉串となり、亡くなった方が仏様ではなく神様になります。
専門知識を持った当社担当スタッフが対応しますので、ご安心ください。
専門知識を持った当社担当スタッフが対応しますので、ご安心ください。
神道のお葬式に必要なものはなんですか?
仏教葬と変わりません。遺影写真と役所届け用のお認め印があれば、お葬式をすることができます。
神式でも焼香をするのですか?
神式では仏式のように焼香はしませんが玉串奉奠をします。焼香の替わりに榊の小枝を、胸の高さに捧げて枝先を霊前に向け、玉串台へ上げてから二礼二拍手(弔事の場合は音をたてない)の後一礼して祭壇に向かったまま、二、三歩下がって体の向きを改め神職、遺族に一礼して退室します。
(注)天理教及び金光教は四拍手です。
(注)天理教及び金光教は四拍手です。
神葬祭の時、神官さんにお礼を包みたいのですが、表書きをどの様に書いたらよろしいでしょうか?
一般的には、「御礼」として表書きしています。
同じ神事でも地鎮祭、落成式のような祝事の時は、「祝詞料」としたり「御神酒料」「初穂料」とする事もあります。
弔事の時は、御礼と表書きしても間違いとは言えませんが、「御祭祀」となさればよろしいかと思います。
同じ神事でも地鎮祭、落成式のような祝事の時は、「祝詞料」としたり「御神酒料」「初穂料」とする事もあります。
弔事の時は、御礼と表書きしても間違いとは言えませんが、「御祭祀」となさればよろしいかと思います。
なぜ焼香するのですか?
香をたくというのは俗人である。私達のけがれをとりはらって清浄になり心を正して仏に接するためであります。また、線香も同じ意味です。
焼香の作法を教えてください。
焼香は(1)回し焼香と(2)出焼香の二通りの仕方があります。
(1)回し焼香は焼香器が回ってきましたら姿勢を正して頭礼(かるく頭を下げる、合掌礼はしない)
続いて抹香をつまみ(回数は宗派により1~3回)焚きます。終わって念珠を正しくかけ合掌礼(念仏は自分の耳に聞こえる程度)し、次の人に焼香器を渡します。
(2)出焼香(呼出し焼香)の場合は、まず導師に合掌礼して焼香の前に進み姿勢を正しく頭礼し、続いて焼香し念珠を正しくかけ合掌、向きを変え導師に一礼して席へ戻ります。
地域や宗派によって異なります。本当に大事なのは心を込めて焼香をしてあげるのが、一番でしょう。
(1)回し焼香は焼香器が回ってきましたら姿勢を正して頭礼(かるく頭を下げる、合掌礼はしない)
続いて抹香をつまみ(回数は宗派により1~3回)焚きます。終わって念珠を正しくかけ合掌礼(念仏は自分の耳に聞こえる程度)し、次の人に焼香器を渡します。
(2)出焼香(呼出し焼香)の場合は、まず導師に合掌礼して焼香の前に進み姿勢を正しく頭礼し、続いて焼香し念珠を正しくかけ合掌、向きを変え導師に一礼して席へ戻ります。
地域や宗派によって異なります。本当に大事なのは心を込めて焼香をしてあげるのが、一番でしょう。
なぜ数珠を持つのですか?
数珠、誦珠、呪珠などと書きます。
数珠の数は108個であり、これは108の煩悩(ぼんのう)を絶つという願いからです。その108個を基本とし、半分の54個、4分の1の27個のものがあります。
また、数珠の光徳は、仏と私達衆生の間に立って仏道修行を助けてくれる法具であるといえます。
数珠の数は108個であり、これは108の煩悩(ぼんのう)を絶つという願いからです。その108個を基本とし、半分の54個、4分の1の27個のものがあります。
また、数珠の光徳は、仏と私達衆生の間に立って仏道修行を助けてくれる法具であるといえます。
宗派によって焼香のきまりがあるのですか?
真宗大谷派(代表的東別院)では焼香は2回。浄土真宗本願寺派(代表的西別院)では、焼香1回。この二つの宗派はお線香は立てないで横にねせる。
曹洞派(代表的高龍寺)は焼香2回、お線香は1本立てる。浄土宗、日蓮宗には、決まりはありません。
なお、会葬者の多い時は1回でもかまいません。
曹洞派(代表的高龍寺)は焼香2回、お線香は1本立てる。浄土宗、日蓮宗には、決まりはありません。
なお、会葬者の多い時は1回でもかまいません。
焼香の回数に決まりはあるの?
これは宗派によっても異なりますし、寺院の教えにより若干異なることもあります。
基本的には
天台宗・・・ 1回または3回
真言宗・・・ 3回
臨済宗・・・ 1回
曹洞宗・・・ 2回(1回目は額におしいただき、2回目はいただかずに焼香する)
浄土宗・・・ 特にこだわらない
浄土真宗 本願寺派・・・ 1回(額におしいただかずに)
真宗 大谷派・・・ 2回(額におしいただかずに)
日蓮宗・・・ 1回または3回
基本的には
天台宗・・・ 1回または3回
真言宗・・・ 3回
臨済宗・・・ 1回
曹洞宗・・・ 2回(1回目は額におしいただき、2回目はいただかずに焼香する)
浄土宗・・・ 特にこだわらない
浄土真宗 本願寺派・・・ 1回(額におしいただかずに)
真宗 大谷派・・・ 2回(額におしいただかずに)
日蓮宗・・・ 1回または3回
新仏(にいぼとけ)ができたので仏壇を買ったが、神棚のある部屋に安置してもよいのか?
かまいません。ただし、お仏壇と神棚が向かい合わせになる場所だけは避けてください。お仏壇を置く場所は、静かな部屋が理想です。安置する方角としては、南面北座説(南向きに安置、北側に座り礼拝する)と西方浄土説(東向きに安置し、西に向かって礼拝する)などがあります。お仏壇の保存も考慮して、南向きか東向きで、なるべく静かな部屋に安置すると良いでしょう。
仏壇の向きは?
(1)西方浄土 仏壇を東向きに安置し西に向かって手を合わせる
(2)南面北座 仏壇を南向きに安置し北に向かって手を合わせる
(3)本山中心型 その宗派の本山のある方角に向かって手を合わせるように安置する
という言われがありますがそれほど厳密ではありません。
なぜなら今の住宅事情等で難しい場合もあるからです。
(2)南面北座 仏壇を南向きに安置し北に向かって手を合わせる
(3)本山中心型 その宗派の本山のある方角に向かって手を合わせるように安置する
という言われがありますがそれほど厳密ではありません。
なぜなら今の住宅事情等で難しい場合もあるからです。
服喪中ですが、友人の結婚式に招待されています。出席はひかえたほうがよいでしょうか?
忌明け前の出席はひかえたほうが良いでしょう。最近は服喪期間が簡略化されていますが、一応の目安として、死後七七日(49日)までを「忌」の期間、一周忌までを「服」の期間とし、この二つを合わせて「喪」といいます。「忌」は重い喪で、この期間中は慶事への出席は遠慮するのが一般的です。
よく「忌中」とか「喪中」とかいいますが、どう違うのでしょうか?
「忌中」とは、近親者が死亡した場合、死者の汚れをつけている期間であり、不吉なこと等を避けるため慎んでいる期間であり、時に死後49日間をいいます。
「喪中」とは、死後ある一定期間、家に閉じこもり、祝事や交際を差し控えている間のことをいいます。年賀状は一年欠礼しているのが現状です。
「喪中」とは、死後ある一定期間、家に閉じこもり、祝事や交際を差し控えている間のことをいいます。年賀状は一年欠礼しているのが現状です。
納骨・埋骨について教えてください。
火葬にしたお骨は、一度自宅に持ち帰ります。いつ納骨するかは土地によって違いがありますが、忌明けの四十九日に行なうのが一般的です。法要の後、墓地で納骨式を行ないます。僧侶の指示に従い遺骨を墓の中に安置し、僧侶の読経の後参列者が焼香し、納骨式を終わります。
最近は核家族化、少子高齢化などを背景に永代供養をする方が増えてきているようです。納骨堂は公営のところやお寺、本山のものがあり場所によっては他宗派を受け付けないところもありますから注意してください。詳しくは当社担当スタッフに問い合わせください。
最近は核家族化、少子高齢化などを背景に永代供養をする方が増えてきているようです。納骨堂は公営のところやお寺、本山のものがあり場所によっては他宗派を受け付けないところもありますから注意してください。詳しくは当社担当スタッフに問い合わせください。
法要は何のために行うのですか?
法要とは、仏さまを供養するという意味の仏教用語で、追善供養ともいいます。
法要は故人の冥福を祈り、その霊を慰めるために営みます。
冥福とは、冥途の幸福のことで、故人があの世でよい報いを受けてもらうために、この世に残された者が仏さまの供養をするのです。
また一方で法要は、生きている私たちが在りし日の故人を偲び、故人への感謝の思いを新たに、充実した日々がおくれるよう自分自身を見つめ直す場でもあります。
法要は故人の冥福を祈り、その霊を慰めるために営みます。
冥福とは、冥途の幸福のことで、故人があの世でよい報いを受けてもらうために、この世に残された者が仏さまの供養をするのです。
また一方で法要は、生きている私たちが在りし日の故人を偲び、故人への感謝の思いを新たに、充実した日々がおくれるよう自分自身を見つめ直す場でもあります。
法要と法事は同じ意味ですか?
厳密に言えば、法事は追善供養のほかに、祈願、報恩などの仏法行事全般のことをいいます。それに対して法要は、追善を目的とした行事のことをいいますが、いまは同じ意味で使われています。
一般的には、故人への供養や、年忌法要をつとめることが法事と呼ばれています。
一般的には、故人への供養や、年忌法要をつとめることが法事と呼ばれています。
供養とは?
供養とは、お仏壇やお墓、寺院などで、仏さまや故人に供物や花を供え、お経やお線香をあげ、手を合わせおまいりすることです。
その善行(ぜんこう)(善い行い)の功徳(くどく)を積み、その功徳を回向(えこう)することで、自分を含むすべての人々の幸せを祈るものです。
功徳とは、善行の結果として与えられる仏さまの恵みや御利益(ごりやく)のことであり、回向とは、その功徳を自分の悟りのため、さらに他の人の利益のためにめぐらすことです。
また回向とは、仏さまの力によって、功徳を差し向けていただくことでもあります。
その善行(ぜんこう)(善い行い)の功徳(くどく)を積み、その功徳を回向(えこう)することで、自分を含むすべての人々の幸せを祈るものです。
功徳とは、善行の結果として与えられる仏さまの恵みや御利益(ごりやく)のことであり、回向とは、その功徳を自分の悟りのため、さらに他の人の利益のためにめぐらすことです。
また回向とは、仏さまの力によって、功徳を差し向けていただくことでもあります。
先祖供養とは?
先祖供養とは、わが命のルーツに感謝する行為です。
今日私たちがあるのは、ほかならぬ先祖の人々のおかげで、ご先祖の誰ひとり欠けても現在の自分は存在しません。
先祖供養をすることは、自分をあらしめてくれたすべての人に感謝することであるのです。
今日私たちがあるのは、ほかならぬ先祖の人々のおかげで、ご先祖の誰ひとり欠けても現在の自分は存在しません。
先祖供養をすることは、自分をあらしめてくれたすべての人に感謝することであるのです。
中陰とは?
仏教では、人が受胎した瞬間を「生有(しょうう)」、生きている間を「本有(ほんう)」、死の瞬間を「死有(しう)」と呼び、亡くなって次の世界に生まれるまでの四十九日間を「中陰(ちゅういん)」とか「中有(ちゅうう)」と呼んでいます。
この四十九日の間に来世の行き先が決まる、とされています。来世とは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天の六道のことです。
仏教には輪廻転生(りんねてんしょう)という考え方があり、日本ではこの中陰の考え方は仏教習俗として定着しました。
この四十九日の間に来世の行き先が決まる、とされています。来世とは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天の六道のことです。
仏教には輪廻転生(りんねてんしょう)という考え方があり、日本ではこの中陰の考え方は仏教習俗として定着しました。
中陰の法要とは?
中陰の法要は、四十九日の間、初七日(しょなのか)、二七日(ふたなのか)、三七日(みなのか)、四七日(よなのか)、五七日(いつなのか)(三十五日)、六七日(むなのか)、七七日(なななのか)(四十九日)というように、亡くなった命日から数えて七日目ごとに故人を供養します。
これは死者が冥途にいくと、七日ごとに閻魔大王を筆頭にした十王によって審判が行われるという考えからきています。この審判の日に遺族が供養することによって、その善行を積み重ねた追善(ついぜん)が、故人にも及ぶと考えられています。ですから故人が極楽浄土に行けるように、という願いを込めて七日ごとに法要を行うのです。
初七日は、最近では葬儀当日に合わせて行うことが多くなっています。
これは死者が冥途にいくと、七日ごとに閻魔大王を筆頭にした十王によって審判が行われるという考えからきています。この審判の日に遺族が供養することによって、その善行を積み重ねた追善(ついぜん)が、故人にも及ぶと考えられています。ですから故人が極楽浄土に行けるように、という願いを込めて七日ごとに法要を行うのです。
初七日は、最近では葬儀当日に合わせて行うことが多くなっています。
四十九日はなぜ大切なのですか?
中陰の法要の中でも四十九日の法要は、とりわけ重要といわれています。なぜならば四十九日は、故人の行き先が決定する日だからです。
故人には極楽浄土に行って幸せになってもらいたい、と願うのは残された者の自然な感情で、この期間に十分な供養を行なえば故人は成仏できる、と考えられています。
四十九日は、満中陰(まんちゅういん)とも呼ばれ、家族や親族のほか、故人と縁の深かった方々を招いて法要を営みます。
一般的には、この四十九日の法要と合わせて納骨を行う場合が多いです。
四十九日までが忌中(きちゅう)で、この日をもって忌明(きあ)けとなり、それまで喪(も)に服していた遺族が日常生活にもどる日でもあります。
故人には極楽浄土に行って幸せになってもらいたい、と願うのは残された者の自然な感情で、この期間に十分な供養を行なえば故人は成仏できる、と考えられています。
四十九日は、満中陰(まんちゅういん)とも呼ばれ、家族や親族のほか、故人と縁の深かった方々を招いて法要を営みます。
一般的には、この四十九日の法要と合わせて納骨を行う場合が多いです。
四十九日までが忌中(きちゅう)で、この日をもって忌明(きあ)けとなり、それまで喪(も)に服していた遺族が日常生活にもどる日でもあります。
四十九日までの遺族の心得は?
中陰の四十九日間は、遺骨、遺影、白木の位牌を安置し、花や灯明、香炉を置く中陰壇(後飾り壇)を設け、故人が浄土に行けるよう家族でお参りします。七日ごとの法要が無理な場合でも、この期間は中陰壇の前にできるだけ座りお線香をあげ、手を合わせお参りします。
特に閻魔大王の裁きを受けるという三十五日は、丁寧に法要を営むことが多いです。
一般的には四十九日までが忌中(きちゅう)で、この期間は結婚式などのお祝いごとへの出席や、神社への参拝は控えるようにします。
特に閻魔大王の裁きを受けるという三十五日は、丁寧に法要を営むことが多いです。
一般的には四十九日までが忌中(きちゅう)で、この期間は結婚式などのお祝いごとへの出席や、神社への参拝は控えるようにします。
ご遺骨のご安置について
自宅にお骨はどのくらいおいていいの?
実際遺骨を自宅で保管することは法律上禁止されていませんなので期間というのも特にはありません。
自宅でのお骨の向きは?
自宅での遺骨の置き方には特にいわれなどはありません。
自宅での安置は仮納骨と考えられるからです。
考えるのであれば生活に支障のない場所と言われます。
遺骨になってしまっていてもそれは近しい人でありますので、風通しの悪い場所は避けた方がよいでしょう。
皆様のお参りしやすい場所がよいでしょう。
自宅での安置は仮納骨と考えられるからです。
考えるのであれば生活に支障のない場所と言われます。
遺骨になってしまっていてもそれは近しい人でありますので、風通しの悪い場所は避けた方がよいでしょう。
皆様のお参りしやすい場所がよいでしょう。
寺院について
菩提寺(ぼだいじ)とは?
先祖代々の墓や位牌をおき、菩提を弔う寺のことです。
ご葬儀の時にお経をお願いしたり 法要のときなどはご本堂にてお経やお食事などもします。
ご葬儀の時にお経をお願いしたり 法要のときなどはご本堂にてお経やお食事などもします。
菩提寺がなくてもお葬式は出来るんですか?
若い時に東京に来られた方などはご自身の出身地が遠方のため菩提寺様とのお付き合いをもたれない方もおられます。そういった方々の中にはお葬式の時にはご僧侶をお願いしたいという方がいらっしゃいます。その場合 今後のご法事等のご供養事も考慮してご自宅の近くや皆様の集まりやすいご寺院様をご紹介させていただきます。
弊社がご紹介させていただくご寺院様(お坊さん)は寺社仏閣をお持ちでお優しい方ばかりです。
弊社がご紹介させていただくご寺院様(お坊さん)は寺社仏閣をお持ちでお優しい方ばかりです。
菩提寺は遠くにあるのですが、どうすればよいでしょう?
菩提寺様があれば、たとえ遠方であっても、まず菩提寺様にお願いするのが原則です。
多くの場合、日程さえ合えば、菩提寺様のご住職様に来ていただけます。
その際には、お布施に加えて、宿泊費、交通費をご負担になります。
菩提寺様のご住職様のご都合がつかない場合には、菩提寺様からご寺院様をご紹介いただくといいでしょう。 万一、ご紹介いただけないときには、ご住職様のご了解を得て、弊社が同じ宗派のご寺院様を紹介させていただきます。
弊社がご紹介させて戴いたご寺院様にご依頼する場合、戒名(法名)を事前に菩提寺様からお授かりになるのか、ご葬儀の際には俗名(本名)のまま執り行い、後日納骨の際に菩提寺様のご住職様につけていただくかになります。
多くの場合、日程さえ合えば、菩提寺様のご住職様に来ていただけます。
その際には、お布施に加えて、宿泊費、交通費をご負担になります。
菩提寺様のご住職様のご都合がつかない場合には、菩提寺様からご寺院様をご紹介いただくといいでしょう。 万一、ご紹介いただけないときには、ご住職様のご了解を得て、弊社が同じ宗派のご寺院様を紹介させていただきます。
弊社がご紹介させて戴いたご寺院様にご依頼する場合、戒名(法名)を事前に菩提寺様からお授かりになるのか、ご葬儀の際には俗名(本名)のまま執り行い、後日納骨の際に菩提寺様のご住職様につけていただくかになります。
菩提寺がありますが、無宗教葬をすることはできますか?
ご住職と相談する必要があります。
ご家族の要望に応えるお手伝いをさせていただきますので、どんなことでもご相談ください。
ご家族の要望に応えるお手伝いをさせていただきますので、どんなことでもご相談ください。
お布施は、いつどこで渡せばよいのでしょうか?
本来は、葬儀の翌日にお寺へ出向きお渡しします。葬儀の翌日に菓子折を持ちお寺に伺い、お渡しするのが本来です。
しかし、お寺が遠方であったり、葬儀後は何かと多忙であったりしますので、お通夜、ご葬儀のいずれかに、葬儀場でお渡しするケースが多くなりました。
このとき、読経の前に渡すのは避けましょう。葬儀場には、お金を預かってもらえる所はありませんので、お寺様が懐にお布施を入れた状態で、お経を唱えなければならなくなります。お経が終わり、お寺様が控室で一息ついた頃に控室へ伺いしお渡しされるか、お帰りのお見送りのご挨拶の際にお渡ししましょう。
タイミングが難しいようであれば、当社担当スタッフが頃合いを尋ねてご案内いたします。
しかし、お寺が遠方であったり、葬儀後は何かと多忙であったりしますので、お通夜、ご葬儀のいずれかに、葬儀場でお渡しするケースが多くなりました。
このとき、読経の前に渡すのは避けましょう。葬儀場には、お金を預かってもらえる所はありませんので、お寺様が懐にお布施を入れた状態で、お経を唱えなければならなくなります。お経が終わり、お寺様が控室で一息ついた頃に控室へ伺いしお渡しされるか、お帰りのお見送りのご挨拶の際にお渡ししましょう。
タイミングが難しいようであれば、当社担当スタッフが頃合いを尋ねてご案内いたします。
お布施はどのくらい用意すればよいのですか?
菩提寺のご住職に直接お伺うかがいするか、檀家内の年長者の方にご相談ください。
お布施はの金額は、お寺によって様々です。また、頂く戒名によっても異なります。
お檀家の方なら、直接伺っても差支えないようです。
お寺様とのお付き合いがなく、弊社がご導師をお探しする場合は弊社がお寺様へお布施の金額をお伺いします。
お布施はの金額は、お寺によって様々です。また、頂く戒名によっても異なります。
お檀家の方なら、直接伺っても差支えないようです。
お寺様とのお付き合いがなく、弊社がご導師をお探しする場合は弊社がお寺様へお布施の金額をお伺いします。
戒名料とお布施の違いは?
戒名料とは、戒名をいただくお布施のことです。寺院によって違いがございます。
都内ですと、お布施=「ご葬儀の読経」+「戒名」での場合が多いです。
都内ですと、お布施=「ご葬儀の読経」+「戒名」での場合が多いです。
戒名はいついただくのですか?
お通夜の前までに、ご住職様と相談して決めます。ご家族がご住職様と、お話しいただいたき故人様のお人柄などをもとに、戒名を授けていただきます。その後、お通夜(火葬)当日に戒名をお持ちいただきます。本来は、生前に授かるものですが、今では少なくなっているようです。
戒名は必要なの?
もともと戒名(法名、法号)とは、仏門に弟子入りをする誓いの証として師匠から与えられる名前です 浄土真宗では戒律がないので法名 日蓮宗では法号と呼ばれます。
実際に戒名は仏教徒でなければ必要ありません。
ただし寺院に墓地がありご不幸があって故人をその墓地に埋葬するにはその寺院のご住職に戒名を授からなければ埋葬は許可されない場合が多いです。
霊園などで菩提寺様とのお付き合いがなければ戒名を授からなくても埋葬することは可能になります。
実際に戒名は仏教徒でなければ必要ありません。
ただし寺院に墓地がありご不幸があって故人をその墓地に埋葬するにはその寺院のご住職に戒名を授からなければ埋葬は許可されない場合が多いです。
霊園などで菩提寺様とのお付き合いがなければ戒名を授からなくても埋葬することは可能になります。
戒名(法名)には、どんな種類があるのですか?
戒名は真宗では法名(院釈、釈)、日蓮宗では法号(妙法)、その他は戒名と呼ばれています。
戒名は男性(院殿居士、院居士、居士、信士)
女性(院殿大姉、院大姉、大姉、信女)
子供(童子、童女、孩子<がいじ>、孩女)
院殿号は昔なら天皇、皇居、大名やその夫人に限られていました。現代では寺の興隆に貢献した人 または社会に尽くした人に与えられます。
戒名は男性(院殿居士、院居士、居士、信士)
女性(院殿大姉、院大姉、大姉、信女)
子供(童子、童女、孩子<がいじ>、孩女)
院殿号は昔なら天皇、皇居、大名やその夫人に限られていました。現代では寺の興隆に貢献した人 または社会に尽くした人に与えられます。
戒名の費用はどのようになっているのでしょうか?
「信士」「居士」「院号」の順に費用が高くなりますが、戒名料の金額については寺社仏閣や地域によりかなり幅があるのが実情です。
ご奉納の方法もお経料と戒名料が別途になる場合もありますし、お経料に戒名料が含まれる場合もあります。
ご奉納の方法もお経料と戒名料が別途になる場合もありますし、お経料に戒名料が含まれる場合もあります。
お寺にはいつ連絡すればいいのですか?
亡くなられたらすぐに菩提寺様にご一報をお願いいたします。
寺院が遠いのですが、お葬式はそのお寺まで行かないといけないものなのですか?
ご住職様にご葬儀をする場所までお越しになるのをお願いいたします ご住職様がお通夜のときに宿泊する場合は、宿を手配いたします。
菩提寺様が遠方で葬儀に来ることができない場合は、どうするのですか?
菩提寺様の許可を得てから弊社にて、お勤めをされるご導師を紹介いたします。一般的には、菩提寺様より戒名だけをいただき、葬儀当日は弊社で紹介したご導師様に読経していただきます。この場合のお布施費用は、俗名(読経のみ)の金額となります。
お迎え(お車の手配)やお食事の用意については、どのようにすればよいですか?
お迎えについては、ご自身のお車でいらっしゃることもありますし、ハイヤーを手配することもあります。お食事も必要な時と必要のない時がございますので、ご住職様のご予定をお伺いします。
お布施を入れる「袋」はどこで売ってますか?
弊社がご用意いたします・「お車代」や「御膳料」・「塔婆料」の熨斗袋のご用意もありますのでお申し付けください。
各種手続きについて
死亡した場合、役所に提出するものなどはありますか?
家族・親戚は7日以内に死亡診断書(事故死の場合は死体検案書)と死亡届を、死亡した場所の市区町村長に提出しなければなりません。もしくは提出可能な市町村に提出いたします。この届けが受理されると、その人は戸籍から抹消されます。また、受理されると火葬(埋葬)許可証が発行され、これによってはじめて火葬が可能になります。弊社ではこれを代行して行います。
当社で代行手続きをしております。
当社で代行手続きをしております。
埋葬許可証(火葬許可証)について教えてください。
火葬が終わった時に、火葬場で火葬許可証に日時を記入して返してくれます。これが埋葬許可証になります。墓地や納骨堂に骨を収める為の通行証ですから、紛失しないように大切に保存しなければなりません。
交付されてから5年未満であれば、火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらえます。そしてそれを死亡届を出した市町村役場に提出すると、埋葬許可証を再発行してくれます。
※死亡診断書を市役所の戸籍課へ提出し、火葬許可証をいただいてきます。(弊社が手続きを代行いいたします。)
交付されてから5年未満であれば、火葬した火葬場で「火葬証明書」を発行してもらえます。そしてそれを死亡届を出した市町村役場に提出すると、埋葬許可証を再発行してくれます。
※死亡診断書を市役所の戸籍課へ提出し、火葬許可証をいただいてきます。(弊社が手続きを代行いいたします。)
死亡届って?
届出人の記載は優先順位がありますが死亡届を窓口に提出するのは当社で代行いたします。
そして死亡届の届出義務者は法律により次の順序で定められています。
(1)同居親族
(2)同居していない親族
(3)親族以外の同居者、家主、地主または土地家屋の管理人
死亡届は死亡を知った日から7日以内に死亡診断書、または死体検案書を添付して行うこと
(戸籍法86条)*国外での場合は3ヶ月以内
また届出先は死亡者の本籍地、死亡地もしくは届出人の住所地の役所、役場の戸籍係です。
そして死亡届の届出義務者は法律により次の順序で定められています。
(1)同居親族
(2)同居していない親族
(3)親族以外の同居者、家主、地主または土地家屋の管理人
死亡届は死亡を知った日から7日以内に死亡診断書、または死体検案書を添付して行うこと
(戸籍法86条)*国外での場合は3ヶ月以内
また届出先は死亡者の本籍地、死亡地もしくは届出人の住所地の役所、役場の戸籍係です。
死亡記載事項証明書とは?
死亡診断書に死亡届もついている為、間違えられるケースが頻繁にあります。
死亡届の記載事情証明書にはプライバシーに関わることが多く含まれるので特定の使用目的以外では原則として発行されません。
例として民間の生命保険などは発行できない 厚生年金等の遺族年金請求や、郵便局簡易保険(民営化前に限られます。)の請求のためなどで必要となる証明書です。
判断が難しく請求される理由の証明を持参しなくては発行されません。
発行場所や期限は本籍地だと1ヶ月、死亡届を提出した役所では1年間有料での発行となりその後は法務局の発行となります。
死亡届の記載事情証明書にはプライバシーに関わることが多く含まれるので特定の使用目的以外では原則として発行されません。
例として民間の生命保険などは発行できない 厚生年金等の遺族年金請求や、郵便局簡易保険(民営化前に限られます。)の請求のためなどで必要となる証明書です。
判断が難しく請求される理由の証明を持参しなくては発行されません。
発行場所や期限は本籍地だと1ヶ月、死亡届を提出した役所では1年間有料での発行となりその後は法務局の発行となります。
葬儀接待関係
葬儀で返礼品が余ったら、引取ってくれますか?
ムラカミではご利用分の実数精算で余りをお引取りします。お葬式には、不測に備えてある程度多めに御品を用意しておき、ご利用分だけを後で精算する形をとっておりますのでご安心ください。
お返しの品についてですが、会葬御礼と香典返しは違うのですか?
会葬御礼は、香典の有無にかかわらず通夜や告別式に訪れた方へのお礼の気持ちとして、礼状と品をあわせてお渡しするものです。香典返しは、お香典をいただいた方にお礼の気持ちを込めて渡す返礼品を指します。葬儀の当日に渡す「即日返し」と忌明け(49日)に持参・配送する「忌明け返し」の2通りがあります。
葬儀に参列する方の人数に加え、友人、知人、または同僚の香典を預かって弔問される場合などもあり、必要な返礼品の数はお葬式を終えてみなければ数がわからないものです。更には、葬儀後にご自宅を訪れる方もいらっしゃることでしょう。このような事情を踏まえて返礼品についてもムラカミは柔軟に対応いたします。
葬儀に参列する方の人数に加え、友人、知人、または同僚の香典を預かって弔問される場合などもあり、必要な返礼品の数はお葬式を終えてみなければ数がわからないものです。更には、葬儀後にご自宅を訪れる方もいらっしゃることでしょう。このような事情を踏まえて返礼品についてもムラカミは柔軟に対応いたします。
家が狭いので通夜ぶるまいができないのですが、この場合、弔問客へのお礼はどうしたらよいでしょうか?
「通夜返し」といって、粗供養品を渡すのが一般的です。喪家の諸事情であったり、通夜振る舞いの為に使う場所が確保出来なかったといった場合には、通夜振る舞いを省略することも見受けられます 弔問客の飲食に代わるもので、お茶や砂糖・酒などのセットが多いようです。お寿司ですと助六が一般的になります。
精進料理の意味ってなんですか?
元来魚や肉などを食べずに精進した中陰(下記参照)
期間に区切りをつけ日常生活に戻ることから精進落としと言われ魚や肉などの「なまぐさもの」が出されました。
中陰・・・死んでから次の生を得る期間を中陰と呼び
49日間であるとされこの期間は死の穢れが強い時期ということで遺族は祭りなどに出ることなく謹慎して家にこもり、これを忌中と言い四十九日が過ぎるとしたがって忌明けとなり日常生活にもどります。
期間に区切りをつけ日常生活に戻ることから精進落としと言われ魚や肉などの「なまぐさもの」が出されました。
中陰・・・死んでから次の生を得る期間を中陰と呼び
49日間であるとされこの期間は死の穢れが強い時期ということで遺族は祭りなどに出ることなく謹慎して家にこもり、これを忌中と言い四十九日が過ぎるとしたがって忌明けとなり日常生活にもどります。
搬送について
亡くなった後、まずは何をすべきですか?
病院などで亡くなった場合、法律で24時間経過するまでは火葬ができないことになっています。
そのため故人の安置場所を取り急ぎ決める流れになり、自宅・斎場・専用施設などが主な候補としてあがります。この時に慌てることなく慎重に対応することが重要です。「一度は自宅に帰してあげたい」「利便性を優先して葬儀場に直接連れていきたい」など、ご希望がおありでしょう。また、同時にお葬式をどこで行うかなど、全体の流れを通して最適な安置場所を考える必要がありますので、この時には専門的な情報が色々と必要になります。ご依頼の有無にかかわらず、当社までご連絡ください。
一緒に付添いたいなどのご要望にも応じて最適なご提案をいたします。
そのため故人の安置場所を取り急ぎ決める流れになり、自宅・斎場・専用施設などが主な候補としてあがります。この時に慌てることなく慎重に対応することが重要です。「一度は自宅に帰してあげたい」「利便性を優先して葬儀場に直接連れていきたい」など、ご希望がおありでしょう。また、同時にお葬式をどこで行うかなど、全体の流れを通して最適な安置場所を考える必要がありますので、この時には専門的な情報が色々と必要になります。ご依頼の有無にかかわらず、当社までご連絡ください。
一緒に付添いたいなどのご要望にも応じて最適なご提案をいたします。
亡くなった後は、どのような流れになりますか? 一般的なものを教えてください。
故人を一度ご自宅にお連れし布団にお寝かせするのが一般的です。病院などから故人を移送する車の手配やご自宅へ安置する人手が必要になります。この時に病院で車を手配してくれる場合もありますが、これをどこかの葬儀社が請負う場合も多く見られます。その後の段取りのこともありますので、葬儀を依頼する葬儀社が決まっている場合には、最初からお任せするとスムーズです。また、住宅事情などで自宅に安置が難しい時はご相談ください。当社は霊安室(やすらぎの間)を完備しております。
他に葬儀式場や安置施設などをご提案いたします。
他に葬儀式場や安置施設などをご提案いたします。
亡くなった後は、葬儀社に連絡してどのように故人をお迎えに来てくれますか?
病院によっては夜間でも、大切な方のお体を搬送する準備をするように言われます。
弊社をお選び頂けるのであれば、直ちにフリーダイヤル(0120-711-556)へご連絡ください。
深夜、早朝にかかわらず、直ちに病院へお迎えに参ります。
寝台車へは、1~2名様がご同乗頂けます。
病院から寝台車の手配をしましょうか?と言われることがあります。
病院が搬送してくれる訳ではなく、病院出入りの葬儀社が搬送するのでもちろん費用が生じます。葬儀社がお決まりの場合は、お断りいただくのが賢明です。
弊社をお選び頂けるのであれば、直ちにフリーダイヤル(0120-711-556)へご連絡ください。
深夜、早朝にかかわらず、直ちに病院へお迎えに参ります。
寝台車へは、1~2名様がご同乗頂けます。
病院から寝台車の手配をしましょうか?と言われることがあります。
病院が搬送してくれる訳ではなく、病院出入りの葬儀社が搬送するのでもちろん費用が生じます。葬儀社がお決まりの場合は、お断りいただくのが賢明です。
深夜でも、病院から搬送しないといけないのですか?
病院により事情が異なりますので絶対ではありませんが、深夜に必ず搬送を強制されることは少ないと思います。深夜でも搬送をしなければいけないのではなく病院側は何時にお迎えが来るのかを確認されたいのです。
規模の大きな病院の場合は、霊安室がいくつもあり、翌日まで預かってくれる所もあります、遠方から家族が向かっているなどの理由があれば時間を取れる場合もあります。
しかし、ドライアイスの処置なども必要なので、なるべく早めに搬送することをおすすめします。
弊社は、夜間、早朝のいつ何時でも寝台車でお迎えに伺う準備が整っています。
深夜でも、ご遠慮なさらず、フリーダイヤル(0120-711-556)へご連絡ください。
規模の大きな病院の場合は、霊安室がいくつもあり、翌日まで預かってくれる所もあります、遠方から家族が向かっているなどの理由があれば時間を取れる場合もあります。
しかし、ドライアイスの処置なども必要なので、なるべく早めに搬送することをおすすめします。
弊社は、夜間、早朝のいつ何時でも寝台車でお迎えに伺う準備が整っています。
深夜でも、ご遠慮なさらず、フリーダイヤル(0120-711-556)へご連絡ください。
ご安置とお守りについて
本人が気に入っていた服を、最後に着させたいのですが。
事前にご用意をお願いいたします。
死後、人の体は硬直を始めます。状態によっては、私どもが故人様と対面してからでは、硬直が進み着せ替えが困難な場合があります。
(湯灌を行いお体を柔らかくする方法もありますが)
事前に支度ができるのであれば、病院で最後の処置をして頂く際に看護師さんにお願いしてください 硬直が始まる前に、処置と合わせて、お着替えをして頂けます。
死後、人の体は硬直を始めます。状態によっては、私どもが故人様と対面してからでは、硬直が進み着せ替えが困難な場合があります。
(湯灌を行いお体を柔らかくする方法もありますが)
事前に支度ができるのであれば、病院で最後の処置をして頂く際に看護師さんにお願いしてください 硬直が始まる前に、処置と合わせて、お着替えをして頂けます。
病院の支払いは、その時にしなければならないのですか?
一般的には、後日支払います。
もしもの時が、平日の日中であれば、「後日、落ち着いた時に」と請求書を渡されます。
夜間や、祝日の場合は、後日請求書が送られてきます。
支払い期限は病院により異なりますので、後日に病院に確認されるのが良いでしょう。
もしもの時が、平日の日中であれば、「後日、落ち着いた時に」と請求書を渡されます。
夜間や、祝日の場合は、後日請求書が送られてきます。
支払い期限は病院により異なりますので、後日に病院に確認されるのが良いでしょう。
自宅に安置する際の注意事項は?
夏場であれば、ご安置はエアコンのある部屋をおすすめいたします。ご弔問の方が多い場合は、お招きしやすい場所を選びます。
ご自宅がマンションでエレベーターを利用される場合は、エレベーター室を広くするためにトランクルームの扉を開ける鍵が必要になります。事前に管理人さんへご相談していただけるとスムーズにご安置することができます。
ご自宅がマンションでエレベーターを利用される場合は、エレベーター室を広くするためにトランクルームの扉を開ける鍵が必要になります。事前に管理人さんへご相談していただけるとスムーズにご安置することができます。
自宅安置する場合は、ベッドでもよいのでしょうか?
ベッドで問題ございません。「ご安置は布団で」というイメージがございますが、 最後は生前お使いになっていた、使い慣れたところでお休みになることをおすすめいたします。
自宅に連れて帰れないのですが。
当社にて故人様をお預かり出来る霊安室「やすらぎの間」を完備しております。
何なりとお申し付けください。
もしくはご希望の葬儀場(霊安室完備)か、提携霊安室(安置所)でお預かりいたします。
何なりとお申し付けください。
もしくはご希望の葬儀場(霊安室完備)か、提携霊安室(安置所)でお預かりいたします。
自宅に安置する場合は、何を準備したらよいのでしょうか?
お寝かせする敷布団と掛け布団をご用意ください。
枕とシーツはご用意しておりますので大丈夫です。
安置するお部屋は、お客様を通しやすい部屋が良いと思います。その時お布団は、枕を北向きにするのが習わしです。住宅事情等で、北向きが困難な場合は、西向きでもかまいません。もしくは普段お休みをされてる位置でのご案内をいたします。
お線香を手向ける支度などは、全て弊社がご用意いたします。 ※仏式の場合
枕とシーツはご用意しておりますので大丈夫です。
安置するお部屋は、お客様を通しやすい部屋が良いと思います。その時お布団は、枕を北向きにするのが習わしです。住宅事情等で、北向きが困難な場合は、西向きでもかまいません。もしくは普段お休みをされてる位置でのご案内をいたします。
お線香を手向ける支度などは、全て弊社がご用意いたします。 ※仏式の場合
お葬式の日まで数日空いているのですが、大丈夫なのでしょうか?
ご遺体が傷まぬように、弊社スタッフが毎日ドライアイスを交換し、毎日お体の状態を確かめますのでご安心ください。
お葬式の日までお線香の火を絶やしてはいけないものなのですか?
ご家族様のお体のことを考え、夜通しでお線香の番をすることは、現在ではあまり行われておりません。日中でも人の目がないときは、皆様の体調と防火の観点から火を消しておかれることをおすすめいたします。また、ムラカミでは巻き方の線香をご用意しております。巻き方の線香は約10時間ほど燃焼いたしますので日中はお線香の火を絶やさないようにお守りできます。
故人は北枕にしなければいけないのですか?
仏式において御釈迦様が入滅(亡くなられた)ときの姿勢
「頭北面西右脇臥」にならい頭部を北に顔を西に向ける姿勢が基本とされますが、一般的には頭部を北か西へ向けご安置します。
北もしくは西の方角に頭部を向けることが難しい場合は当社担当スタッフがご身内の方とご相談の上安置させていただきます。
「頭北面西右脇臥」にならい頭部を北に顔を西に向ける姿勢が基本とされますが、一般的には頭部を北か西へ向けご安置します。
北もしくは西の方角に頭部を向けることが難しい場合は当社担当スタッフがご身内の方とご相談の上安置させていただきます。
神棚のある部屋へ安置を予定していますが、宗教上問題ありませんか?
弊社にて、「神封じ」(神棚を半紙など白いもので一時的に覆う)を行い対応することで、宗教上の問題はなくなります。
なぜ神棚に白紙を貼るのですか?
神道では死は穢れを意味し、その穢れを除くため、家の神棚に白紙を貼るのです。貼るときは、遺族ではなく、穢れの及んでいない他人にしてもらうしきたりになります。
扉のある神棚や御霊舎は扉を閉め、半紙を縦に貼ります。
扉のない神棚は、祭壇の上部から半紙を貼りさげて、御神体を隠します。
そのまま忌明まで開けないようにし、お参りも控え、供物、御神酒、灯明もあげません。
扉のある神棚や御霊舎は扉を閉め、半紙を縦に貼ります。
扉のない神棚は、祭壇の上部から半紙を貼りさげて、御神体を隠します。
そのまま忌明まで開けないようにし、お参りも控え、供物、御神酒、灯明もあげません。
故人が好きだったお肉やタバコをお供えしてもいいですか?
はい、ぜひお供えください。お供え物に決まりはありません。お供えの御飯は、ご家族のお食事の際、ご一緒に交換される方が多いようです。
白い布を顔に乗せないといけないのですか?
昔からの習わしで特に決まりは有りません 白い布の名称は「打ち覆い」とも呼ばれ昔の死者全体を覆うための大きい布のことで、現在の顔にかける白い布はその名残だとされています。
自宅がマンションなのですが連れて帰れるでしょうか。
マンションやエレベーターのない団地でも可能です。
ご納棺は自宅ではできない場合もございますので、式場などにてご納棺を提案させていただいております。
ご納棺は自宅ではできない場合もございますので、式場などにてご納棺を提案させていただいております。
料金について
お葬式に掛ける費用を、事前に知ることはできますか。
事前にご相談させていただき、何時でもお見積もりいたします。
お客様のご希望に合わせまして様々なお見積書を作成いたします。
どうぞお気軽にお申し付けください。
お客様のご希望に合わせまして様々なお見積書を作成いたします。
どうぞお気軽にお申し付けください。
葬儀の際に追加料金が発生するとよく聞きますが大丈夫でしょうか?
ご安心ください 当社は事前のお打ち合わせにて様々なお話をさせていただいております。
お客様からの特別なご要望(バスの追加等)がない場合 追加料金は一切発生いたしません。
お客様からの特別なご要望(バスの追加等)がない場合 追加料金は一切発生いたしません。
葬儀費用の平均は、どのくらいですか?
財団法人日本消費者協会がまとめた資料によりますと
第9回「葬儀についてのアンケート調査」報告書 2010年(平成22年)11月
葬儀費用の全国平均は、約199.9万円です。
(※祭壇、人件費、飲食費、返礼品、式場使用料、お坊さんへのお礼などを含む)
平均から受ける印象は様々にあると思われますが、葬儀費用は葬儀社が決めるものではなく、お客様が選ぶものです。そのため金額は予算にあわせて調整できるのが一般的です。
規模・場所・形式などを検討しながら金額を算出する必要があります。平均はあくまで参考程度に留め実際の費用に関しては、当社担当スタッフまでご相談ください。ご希望をお伺いしながら、過不足のないご提案・お見積りをいたします。
第9回「葬儀についてのアンケート調査」報告書 2010年(平成22年)11月
葬儀費用の全国平均は、約199.9万円です。
(※祭壇、人件費、飲食費、返礼品、式場使用料、お坊さんへのお礼などを含む)
平均から受ける印象は様々にあると思われますが、葬儀費用は葬儀社が決めるものではなく、お客様が選ぶものです。そのため金額は予算にあわせて調整できるのが一般的です。
規模・場所・形式などを検討しながら金額を算出する必要があります。平均はあくまで参考程度に留め実際の費用に関しては、当社担当スタッフまでご相談ください。ご希望をお伺いしながら、過不足のないご提案・お見積りをいたします。
葬儀費用の注意点は、どんな所ですか?
広告などにある金額だけで比較しないことが大切です。お客様用に見積られた金額ではない場合、実際との差が必ず生じるといっても過言ではありません。特に先に葬儀社が設定したプランでは、「必要なものがすべて含まれます」「追加料金一切なし」などと広告されますが、必要か不要かの判断をお客様が行ったわけではありません。宗教による違いや専門的な部分を端折ってしまうことは後々お客様が恥をかく恐れがあります。専門家である葬儀社にきちんとご相談いただき、ある程度の予算や希望を伝えて、葬儀費用に理解と納得をしながら進めていくほうが良いでしょう。
必要な葬儀費用は、葬儀社のみならず式場・火葬場・車輌・料理・返礼品・お坊さんへの御礼など多岐に渡ります。
お見積りの段階でお客様のご要望を踏まえてご提案いたしますので、過不足のない最適な金額が算出されます。もちろん、後で膨大な請求をしたりすることもありません。また、予算が心配なときは率直にご相談ください。葬儀費用をできるだけ抑えた形でしっかりとご提案いたします。
必要な葬儀費用は、葬儀社のみならず式場・火葬場・車輌・料理・返礼品・お坊さんへの御礼など多岐に渡ります。
お見積りの段階でお客様のご要望を踏まえてご提案いたしますので、過不足のない最適な金額が算出されます。もちろん、後で膨大な請求をしたりすることもありません。また、予算が心配なときは率直にご相談ください。葬儀費用をできるだけ抑えた形でしっかりとご提案いたします。
ご通知・ご連絡
お医者様から危篤を告げられました。何をすればいいですか?
危篤の連絡は、まず、その場にいない家族や親族に伝え、遠方にいる人には、特に早めに知らせます。親戚は三親等までを目安としますが、疎遠なところは必要ないでしょう。
連絡はまずご家族を最優先に行い、次に親戚の方、本人と親しい友人・知人といった順で連絡します。要は危篤者本人の身になって来ていただく人を決めるということです。けれど、遠方の人や忙しい人に連絡しても、臨終に間に合わないこともあります。そのようなことも考慮して連絡しましょう。
危篤の時間が深夜でも早朝でも、本人と親しい人ならば連絡するのもやむを得ないので「こんな時間に申し訳ございません」や「朝早く申し訳ございません」といった一言を添え連絡します。
(※父母や子供・配偶者の父母は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹は2親等、伯父・伯母(叔父・叔母)・甥・姪・曾孫は3親等、いとこは4親等となります。)
連絡はまずご家族を最優先に行い、次に親戚の方、本人と親しい友人・知人といった順で連絡します。要は危篤者本人の身になって来ていただく人を決めるということです。けれど、遠方の人や忙しい人に連絡しても、臨終に間に合わないこともあります。そのようなことも考慮して連絡しましょう。
危篤の時間が深夜でも早朝でも、本人と親しい人ならば連絡するのもやむを得ないので「こんな時間に申し訳ございません」や「朝早く申し訳ございません」といった一言を添え連絡します。
(※父母や子供・配偶者の父母は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の兄弟姉妹は2親等、伯父・伯母(叔父・叔母)・甥・姪・曾孫は3親等、いとこは4親等となります。)
参列者(お招きしたい方)に、葬儀の日時、場所をどのように連絡をすればよろしいでしょうか?
間違いがないようにFAXでの連絡をおすすめします。連絡用のFAXのご訃報は、弊社にて作成いたします。
短時間で多くの方にお葬式の連絡をする方法を教えてください。
電話連絡は間違いが発生するので、FAXもしくはメールで連絡をします。特に来賓(VIP)へは、まず電話連絡をしてから、FAXもしくは訪問をします。お取引先には、FAXで連絡をします。
個人的なお付き合いの方々へは、友人、クラブ活動などの代表者の方に連絡をして、その方が各関係者へ訃報を連絡していく方法が一般的です。
訃報連絡の文面は弊社で準備をさせていただきます。ご安心ください。
個人的なお付き合いの方々へは、友人、クラブ活動などの代表者の方に連絡をして、その方が各関係者へ訃報を連絡していく方法が一般的です。
訃報連絡の文面は弊社で準備をさせていただきます。ご安心ください。
長年同じ地域に住んでいるのですが、町内会への連絡はいつすればよいのでしょうか?
ご葬儀の規模や場所などによって変わるので、事前にあらかじめ決めていた葬儀社と相談することをおすすめいたします。
<例>
・町会(自治会)会館を利用する、町会にお手伝いを頼む場合
→日程を決める前に連絡・相談をしてください。
・身内(家族)だけで送る場合
→ご葬儀後に連絡を入れる方が多いようです。不安が残るようでしたら
「身内だけで葬儀をするので、会葬をご遠慮していただく」旨を町内会に連絡します。
<例>
・町会(自治会)会館を利用する、町会にお手伝いを頼む場合
→日程を決める前に連絡・相談をしてください。
・身内(家族)だけで送る場合
→ご葬儀後に連絡を入れる方が多いようです。不安が残るようでしたら
「身内だけで葬儀をするので、会葬をご遠慮していただく」旨を町内会に連絡します。
お寺など、お坊さんへの連絡はどうすればよいですか?
菩提寺様がいらっしゃる場合は連絡してご都合を伺い、葬儀日程の調整を行わなければなりません。
遠方の場合でも必ず連絡を入れておくと良いでしょう。その時に近くの同じ宗旨の僧侶をご紹介いただける場合もありますので、お寺(菩提寺)が決まっている場合には関係を保つためにも一報が必要です。
決まったお寺などがない場合は、ご希望に応じて寺院などをご紹介いたします。実際に寺構えがあり、後々の法事のことなども相談できるお寺をご紹介していますので安心してご相談ください。
遠方の場合でも必ず連絡を入れておくと良いでしょう。その時に近くの同じ宗旨の僧侶をご紹介いただける場合もありますので、お寺(菩提寺)が決まっている場合には関係を保つためにも一報が必要です。
決まったお寺などがない場合は、ご希望に応じて寺院などをご紹介いたします。実際に寺構えがあり、後々の法事のことなども相談できるお寺をご紹介していますので安心してご相談ください。
葬儀場所について
式場の金額ってどれくらいかかるものなのですか
火葬場併設の式場になりますと当社の近くの代々幡斎場や堀ノ内斎場などの斎場は、使用するお部屋ににも異なりますが、23万円程度になります。
区営斎場やお坊さんの施設の貸し式場など場所により使用金額が異なりますので当社担当スタッフまでご相談ください。
区営斎場やお坊さんの施設の貸し式場など場所により使用金額が異なりますので当社担当スタッフまでご相談ください。
お葬式をする場所は主にどこがあるのですか?
主に、寺院、斎場、葬儀専用会館、、ご自宅、集会場、ホテルなどです。
お客様の住所や、ご希望に合わせてご提案いたします。
お客様の住所や、ご希望に合わせてご提案いたします。
式場選びのポイントと、費用を抑えるコツってありますか?
「ご自宅の近く、もしくはご希望の地域」、「ご希望の規模(会葬者人数)に対応可能か」、 「予算に見合っているか」の3点が主なポイントとなります。
また、公営式場(区営、みどり会館)、火葬場が併設されている式場(斎場、代々幡斎場・堀ノ内斎場など)は霊柩車やマイクロバスなどが不要になるため、車両費を軽減することができます。弊社では、お客様の住所や、ご希望に合わせてご提案いたします。
また、公営式場(区営、みどり会館)、火葬場が併設されている式場(斎場、代々幡斎場・堀ノ内斎場など)は霊柩車やマイクロバスなどが不要になるため、車両費を軽減することができます。弊社では、お客様の住所や、ご希望に合わせてご提案いたします。
公営式場は誰でも利用できるのですか?
ご利用対象者が決まっておりますので、弊社へお問合せいただければすぐにご返答いたします。 また、ご親戚の中にご利用対象者がいる場合、利用できるケースもございますので、まずはお気軽にお問合せください。
葬儀場選びで悩んでいます。どこにしたら良いのでしょうか?
まずは、地域を決めてください。
まず、どのエリアでお葬式を行うかを決めます。
自宅の近くか、会社に近くか、などです。
規模やご要望にあわせて選ぶのが望ましいのですが、その判断には専門的な情報が必要になります。当社担当スタッフまでご相談ください。
最近は、自宅や集会所よりも葬儀会館などで行われることが多くなっていますが、お客様の想定される規模・ご要望にあわせて検討しなければなりません。ご自宅での葬儀はもちろん、各式場の利便性・規模・交通状況などをふまえ、集会所や自治会館などまで含めた最適なアドバイスをいたします。その他にもご提案いたしますので遠慮なくご相談ください。
まず、どのエリアでお葬式を行うかを決めます。
自宅の近くか、会社に近くか、などです。
規模やご要望にあわせて選ぶのが望ましいのですが、その判断には専門的な情報が必要になります。当社担当スタッフまでご相談ください。
最近は、自宅や集会所よりも葬儀会館などで行われることが多くなっていますが、お客様の想定される規模・ご要望にあわせて検討しなければなりません。ご自宅での葬儀はもちろん、各式場の利便性・規模・交通状況などをふまえ、集会所や自治会館などまで含めた最適なアドバイスをいたします。その他にもご提案いたしますので遠慮なくご相談ください。
公営斎場が式場費用が抑えられると聞いたのですが。
その通りです。
意外に知られていませんが、火葬場併設の総合斎場(代々幡斎場・堀ノ内斎場など)は民間の斎場です。設備は充実していますが、公営と比較すると、料金は幾分高めです。
もちろん、値段に見合ったサービスを期待できます。
各地域に、公営の斎場がありますので、こちらを利用すると、式場費用を抑えたお葬式を行うことができます 世田谷区ですと世田谷区北烏山に[みどり会館」がございます。
意外に知られていませんが、火葬場併設の総合斎場(代々幡斎場・堀ノ内斎場など)は民間の斎場です。設備は充実していますが、公営と比較すると、料金は幾分高めです。
もちろん、値段に見合ったサービスを期待できます。
各地域に、公営の斎場がありますので、こちらを利用すると、式場費用を抑えたお葬式を行うことができます 世田谷区ですと世田谷区北烏山に[みどり会館」がございます。
葬儀場は、お通夜の晩、宿泊できるのですか?
大半の葬儀場は可能です。
お通夜の晩に限り、大半の葬儀場は仮眠がとれます。宿泊施設ではないので、宿泊ではなく仮眠です。貸布団を手配し、お休みいただきます。
貸布団は葬儀場か、葬儀社が手配します。
(一組 平均3675円程度です)一部の斎場や葬儀式場では、宿泊ができないところもありますので、詳しくは当社担当スタッフにお問い合わせください。
お通夜の晩に限り、大半の葬儀場は仮眠がとれます。宿泊施設ではないので、宿泊ではなく仮眠です。貸布団を手配し、お休みいただきます。
貸布団は葬儀場か、葬儀社が手配します。
(一組 平均3675円程度です)一部の斎場や葬儀式場では、宿泊ができないところもありますので、詳しくは当社担当スタッフにお問い合わせください。
宿泊のできない式場なのですが、故人と一晩一緒に過ごしたいのだけれどもどうしたらいいですか?
お通夜終了後に寝台車にてご自宅にお連れし翌日、葬儀の前にお迎えに上がることも可能です。
近所に寺院会館があります。檀家以外でも利用できますか?
当社担当スタッフがお調べいたします。
最近は、寺院内の葬儀場を、檀家外の方にも貸し式場として提供するお寺が多くあります。
どちらの寺院会館かお知らせ頂ければ、当社担当スタッフがお調べいたします。
最近は、寺院内の葬儀場を、檀家外の方にも貸し式場として提供するお寺が多くあります。
どちらの寺院会館かお知らせ頂ければ、当社担当スタッフがお調べいたします。
神社でご葬儀を行うことはできますか?
神道において死とは穢れ(けがれ)とされているため、神様の聖域である神社でご葬儀を行うことはできません。ご自宅または式場にて執り行うのが一般的です。
自宅で葬儀をするメリットを教えてください。
まず、式場使用料が不要であることが分かりやすいメリットです。また、葬儀という不慣れな儀式なので、住み慣れた場所で行うことで、精神面にも良い影響はあると考えることができます。
自宅で葬儀をするデメリットを教えてください。
葬儀用に設計されていないので、受付、会計、待合所、食事の場所などが少なく、天候・気温の影響も受けやすいことがデメリットです。対処方法として、状況に応じて、テントを設置したり、冬場はストーブを用意する方法があります。当社担当スタッフがアドバイスいたしますので、ご安心ください。
自宅でお葬式をする時に一番気をつけるポイントは何ですか?
ご自宅の下見です。ご自宅によって、祭壇の飾り方、受付の場所、食事の場所などが異なり、それに応じて必要な備品が発生すると葬儀費用も変わってくるので、当社担当スタッフによる下見、並びに事前相談をおすすめします。
自宅が葬儀で使用できないことはありますか?
ほとんどありません。棺をご自宅へ入れることができればご葬儀はできます。
ご葬儀の規模などによっては適さない場所もございますが、まずは当社担当スタッフまでご相談ください。
ご葬儀の規模などによっては適さない場所もございますが、まずは当社担当スタッフまでご相談ください。
自宅で葬儀を行う場合、どれくらいのスペースが必要ですか?
祭壇の大きさによりますが、通常は8畳以上のお部屋があれば施行可能です。
それと併せましてお坊さんの方のお控え室や参列者の控え室など当社担当スタッフがご相談させていただきます。
それと併せましてお坊さんの方のお控え室や参列者の控え室など当社担当スタッフがご相談させていただきます。
集会所でお葬式をする時に一番気をつけるポイントは何ですか?
集会場をご葬儀としてお借りできるのかを集会場の責任者にご確認をお願いいたします。
集会所によって、親族控え室の有無、祭壇の飾り方、受付の場所などが異なり、それに応じて必要な備品が発生すると葬儀費用も変わってきます。当社担当スタッフが事前に下見をさせていただきお見積もりを作成いたします。
集会所によって、親族控え室の有無、祭壇の飾り方、受付の場所などが異なり、それに応じて必要な備品が発生すると葬儀費用も変わってきます。当社担当スタッフが事前に下見をさせていただきお見積もりを作成いたします。
集会所が葬儀で使用できないことはありますか?
はい。ございます。事前に確認しておくことをおすすめします。
集会所を葬儀で利用する際は、申し込みはどのようにすればよろしいでしょうか?
地域の集会所は、窓口をしている責任者の方へ申し込みます。マンションなど集合住宅では、管理人さんに申し込みをします。利用料金も含めて、事前に申込み窓口を確認しておくことをおすすめします。
集会所で葬儀をするメリットを教えてください。
まず、使用料が一般的な式場より安価なことがメリットです。また、家から近いことも代表的なメリットです。
集会所で葬儀をするデメリットを教えてください。
葬儀用に設計されていないので、受付、会計、待合所、食事の場所などが少なく、天候・気温の影響も受けやすいことがデメリットです。対処方法として、状況に応じて、テントを設置したり、冬場はストーブを用意する方法があります。当社担当スタッフがアドバイスいたしますので、ご安心ください。
その他
遺言ってどうやってつくるの?
まず遺言できる年齢は満15歳以上となっています。
遺言の方式には大きく分けて 普通方式 と 特別方式 というのがあります。
普通方式には 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 の3種類あり
特別方式には 死亡危急者の遺言 伝染病隔離者の遺言 在船者の遺言 船舶遭難者の遺言 の4種類
これ以外は遺言と認められないとのことです。
(1)自筆証書遺言
遺言者が自分で筆をとり遺言の全文・日付を自書し署名、押印をすることによって作成する。
それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったりした場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。
筆記用具や用紙には特に制限はありません。
また執行のため裁判所の検認が必要となります。
(2)公正証書遺言
遺言者本人の口述に基づき公証人が遺言書を作成する。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
その筆記が正確なことを承認した後に遺言者・証人が各自署名・押印します。
さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。
適格で完全な遺言を作成できる代わりにそれなりの費用が必要となります。
(3)秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにし内容は秘密にして遺言書を作成する。
遺言者が遺言書に署名・押印しその遺言書を封じ遺言書に押した印鑑で封印します。
それを公証人1人および証人2人の前に提出し自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述します。
さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後に公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成します。
遺言書を封印し公証人へ提出するので内容に関しての秘密は守られますがその内容が不適格であるために結局無効となってしまう恐れがあります。
また執行のため裁判所の検認が必要となります。
遺言の方式には大きく分けて 普通方式 と 特別方式 というのがあります。
普通方式には 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 の3種類あり
特別方式には 死亡危急者の遺言 伝染病隔離者の遺言 在船者の遺言 船舶遭難者の遺言 の4種類
これ以外は遺言と認められないとのことです。
(1)自筆証書遺言
遺言者が自分で筆をとり遺言の全文・日付を自書し署名、押印をすることによって作成する。
それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったりした場合には無効なものとなってしまうので注意が必要です。
筆記用具や用紙には特に制限はありません。
また執行のため裁判所の検認が必要となります。
(2)公正証書遺言
遺言者本人の口述に基づき公証人が遺言書を作成する。
公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
その筆記が正確なことを承認した後に遺言者・証人が各自署名・押印します。
さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成されます。
適格で完全な遺言を作成できる代わりにそれなりの費用が必要となります。
(3)秘密証書遺言
遺言の存在自体は明らかにし内容は秘密にして遺言書を作成する。
遺言者が遺言書に署名・押印しその遺言書を封じ遺言書に押した印鑑で封印します。
それを公証人1人および証人2人の前に提出し自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述します。
さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後に公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成します。
遺言書を封印し公証人へ提出するので内容に関しての秘密は守られますがその内容が不適格であるために結局無効となってしまう恐れがあります。
また執行のため裁判所の検認が必要となります。
エンディングノートについて知りたいのですが。
ご自身の考えやご葬儀の希望などを明確に残す為のノートになります。葬儀の為にではなくて、家族の為に残す意志として有効にご活用いただけますよう、市販品のほとんどは質問に対する回答形式になっております。
分骨したいのですが、どの様にすると良いですか?
火葬する際、予め当社担当スタッフにご依頼ください。
どこのホテルやレストランでも、お別れ会をすることが出来るのですか?
対応できない場所もございます。地域、参列人数、交通アクセスなど、ご家族様のご希望にあった場所を提案いたしますので、詳しくはお問合せください。
お別れ会、ホテル葬は、どんな儀式をするのでしょうか?
特に決まりはありません。献花、弔辞(お別れの言葉)、思い出映像、ビュッフェの食事など、完全オーダーメイドだからこそ、経験とノウハウが必要とされます。弊社では、経験豊富な当社担当スタッフが対応いたします。
お別れ会は密葬を済ませてから、何日後を目安として行いますか?
四十九日までに行うことが多くなっております。決まりはありませんので、準備やご都合を考え日程を調整することをおすすめします。
お香典は受け付けますか?
個人で執り行う場合は、お香典を受け付けることが多いです。企業が執り行う場合は、税務処理もあるので、会社ごとに異なります。
供花は受け付けますか?
ほとんどの方が受け付けております。
もし各種披露宴と葬儀が重なった場合どうしたらよいのでしょか?
これはとても難しい判断です。
まして自分の友人の晴れの席ということになればもちろん、そうでなくても明るい席に魅かれるのは当然でしょう。
しかし披露宴はスタート、告別式はゴールです。できるだけ大切な方の最期の儀式に出席してあげたいものです。
まして自分の友人の晴れの席ということになればもちろん、そうでなくても明るい席に魅かれるのは当然でしょう。
しかし披露宴はスタート、告別式はゴールです。できるだけ大切な方の最期の儀式に出席してあげたいものです。





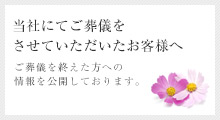
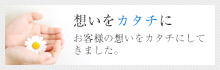
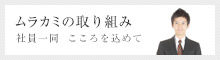
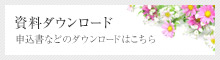
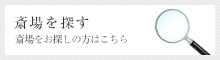

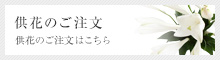

 0120-711-556
0120-711-556  0120-711-556
0120-711-556